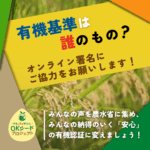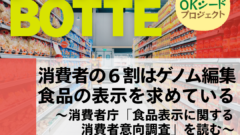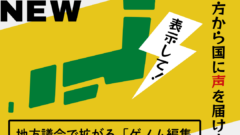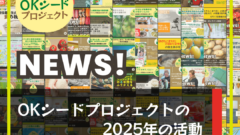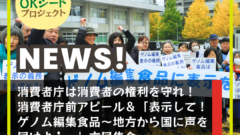今回のたねまきコラムでは、植物学者のKana Koa Weaverさんが登場!
今年の6月に開催された「ローカリゼーションデイ日本2025」のOKシードプロジェクト主催の分科会をSeedおじさんと共にオーガナイズドしてくださったKanaさんに、「たねのローカリゼーション〜ゆるやかにつながる未来会議」についてレポートしていただきました!
植物学者、ハーブ研究家。一児の母。
世界を旅しながら、各地の植物の美しさ、種の多様性、植物にまつわる文化の多様性を次世代に手渡す方法について探究。
東京大学大学院修士、オランダエラスムス大学社会科学研究所修士。カリフォルニア大学サンタクルーズ校環境学博士課程単位取得退学。国際民俗生物学会所属。2024年より米国のSeed Library Networkと協力して日本国内のシードバンク・シードライブラリーマップ作成開始。
現在は米国カリフォルニア州バークレーで、パートナー(映画「EDIBLE CITY エディブル・シティ〜都市を耕す」に登場)と8歳の息子と植物たちと暮らす。好きな食べ物はパイナップルグァバ。
 6月6月にオンライン開催されたローカリゼーションデイ日本2025にて、OKシードプロジェクト主催の分科会として「たねのローカリゼーション〜ゆるやかにつながる未来会議」が開催されました。多くの方にご参加いただき、「たね」という大切なテーマを共有することができた豊かな時間でした。
6月6月にオンライン開催されたローカリゼーションデイ日本2025にて、OKシードプロジェクト主催の分科会として「たねのローカリゼーション〜ゆるやかにつながる未来会議」が開催されました。多くの方にご参加いただき、「たね」という大切なテーマを共有することができた豊かな時間でした。
当日は最初に、OKシードプロジェクト事務局長の印鑰智哉さんから日本の種の現状についてお話いただきました。日本の種を守っていくことの大切さを共有した後、後半は富士山麓有機農家シードバンクのSeedおじさんこと鈴木一正さんと一緒に、日本の種を保全し継いでいくための取り組みの事例のひとつとして、地域のコミュニティシードバンクやシードライブラリーを主催する方々からお話を伺いました。
地域のコミュニティで種を共有するための仕組みは、古くから世界各地でさまざまな形式で存在してきました。なかでも近年、世界的に広まりを見せているのがコミュニティシードバンク・シードライブラリー(種の図書館)です。これは、図書館やカフェや市民センターなどの施設の一角にさまざまな植物の種が詰まった棚を設置して、家庭菜園を楽しみたい人などが誰でも自由に種を持ち帰って庭や畑に植えることができるという仕組みです。原則は“Borrow, Save, & Share(種を持ち帰って育てる・種採りをする・とれた種を共有する)”。多くの種はドネーション(寄付)で集められており、自家採種した種を持ち寄ったり、自慢の種コレクションを寄贈する人もいます。
コミュニティシードバンクやシードライブラリーがある場所は家庭菜園や農業を楽しむ人々の集う場所となっており、種の交換会が行われたり、ガーデニングや種採りのワークショップが開催されたり、種だけでなくさまざまな知識や技術が交換できる場所になっています。「今年は気温が高いからこの作物が向いている」「このトマトはとても美味しかった」「このかぼちゃの種はおばあちゃんにもらった特別な種だ」「この豆にはこういう土壌が向いている」「この花の種には言い伝えがあってね…」など、種とともにさまざまな対話がその場でなされます。シードバンクやシードライブラリーは、種と大地、人と人、地域と物語をつなぎ、種とそこに詰まった生命の記憶を未来の世代に伝える仕組みなのです。
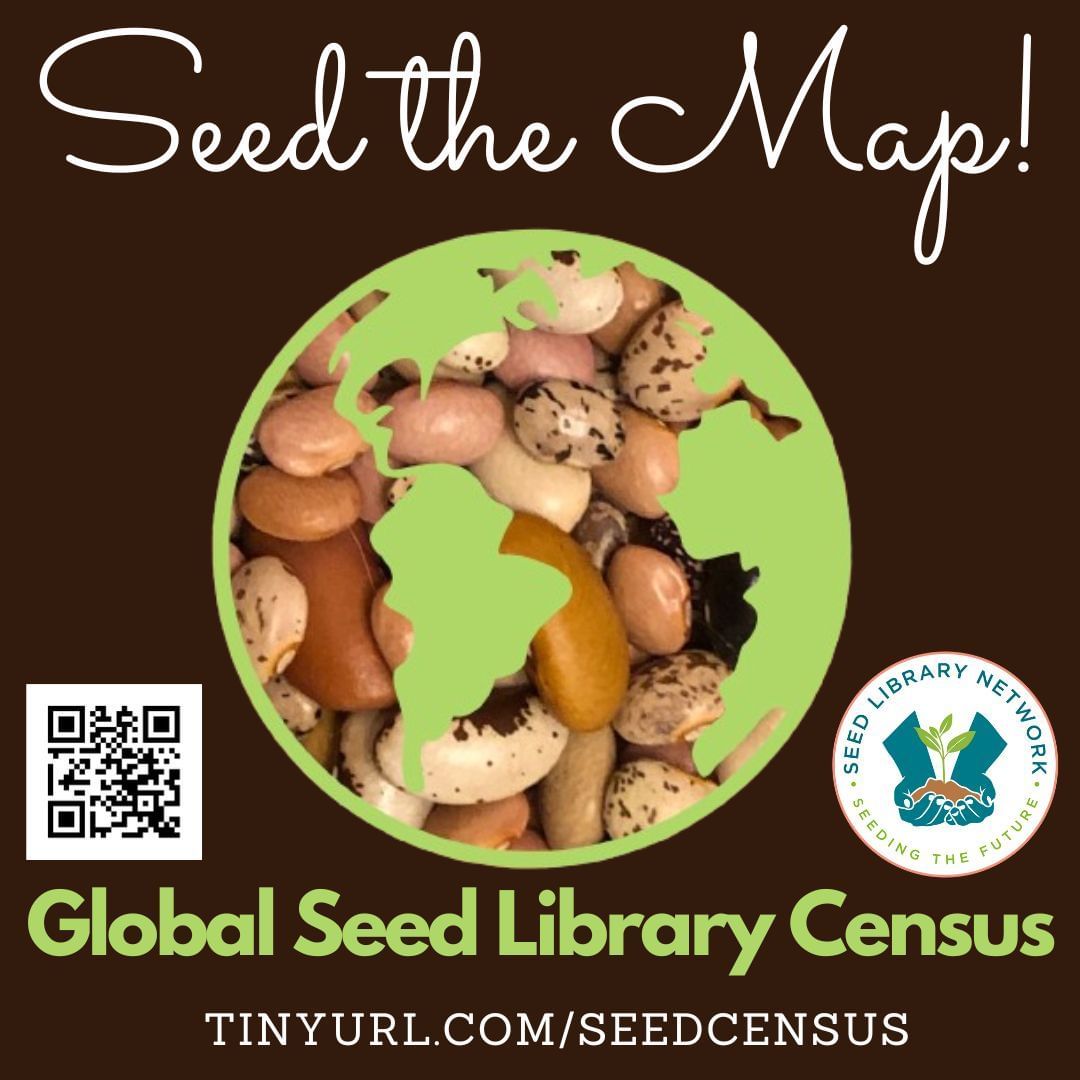 昨年、アメリカに拠点を置く国際シードライブラリーネットワークの要請のもと、多くの方々のご協力をいただきながら、日本のシードバンクやシードライブラリーのマッピング(地図づくり)を行いました。これまでに日本全国・世界各地から65件の拠点からご登録いただいています。ローカリゼーションデイ2025では、そのなかの3拠点から取り組みについてご報告をいただきました(「たねとみつばち 土と太陽」の白金丈英さん、愛知アーバン・パーマカルチャーの榊笙子さん、フォレスト・ガーデンプロジェクトの力武若葉さん、はままつ種ねっとわーくの川田忍さん/ヘチマおじさん)。それぞれの地域ごとの多様で豊かな取り組みを知ることができ、参加者のみなさんとともに多くのインスピレーションを受け取ることができてたいへん盛り上がりました。また、各地の取り組みの内容は多様でも、みなそれぞれ種に対する熱い思いを携えていることを共有することができ、種を愛する仲間としてのつながりやあたたかさを感じる時間となりました。配信のコメント欄でも、世界・日本各地の種に関心のある方々のお声を聞くことができました。
昨年、アメリカに拠点を置く国際シードライブラリーネットワークの要請のもと、多くの方々のご協力をいただきながら、日本のシードバンクやシードライブラリーのマッピング(地図づくり)を行いました。これまでに日本全国・世界各地から65件の拠点からご登録いただいています。ローカリゼーションデイ2025では、そのなかの3拠点から取り組みについてご報告をいただきました(「たねとみつばち 土と太陽」の白金丈英さん、愛知アーバン・パーマカルチャーの榊笙子さん、フォレスト・ガーデンプロジェクトの力武若葉さん、はままつ種ねっとわーくの川田忍さん/ヘチマおじさん)。それぞれの地域ごとの多様で豊かな取り組みを知ることができ、参加者のみなさんとともに多くのインスピレーションを受け取ることができてたいへん盛り上がりました。また、各地の取り組みの内容は多様でも、みなそれぞれ種に対する熱い思いを携えていることを共有することができ、種を愛する仲間としてのつながりやあたたかさを感じる時間となりました。配信のコメント欄でも、世界・日本各地の種に関心のある方々のお声を聞くことができました。
また、分科会の最後には「ゆるやかにつながる たねのなかま」への参加の呼びかけが行われました。種を継ぐ作業は、楽しい一方で地道な作業も多く、活動の継続が難しく感じられる場面も少なくありません。そんな時、他の地域の仲間と情報交換ができたり、励ましあえたりできるつながりを感じられると、活動を続けるうえでの大きな力になります。地域が違ってもシードバンクやシードライブラリーの直面する課題には共通するものも多く(種が循環する仕組みづくり、品質管理の難しさなど)、ひとりの工夫や解決法が多くの人の支えになる場面も多々あります。また、種を継ぐことに興味がある人にとっては、自分の住む場所の近隣地域でどんな活動が行われているのかを知る手掛かりになります。日本各地にはすでに種のつながりや素晴らしいコミュニティー、ネットワークが存在していますが、こうした今回のような呼びかけが、今後種の取り組みを広げ、深めていくための一助となればという願いが込められています。
植物の種は、世界の大きな繋がりを通じて育まれます。光、水、風、鉱物、微生物、虫、獣、人々の営みや祈り…そしてそれらの記憶は種の中に刻み込まれ、未来に継がれていきます。種は、生命の歴史の情報が詰まった図書館のようなものです。
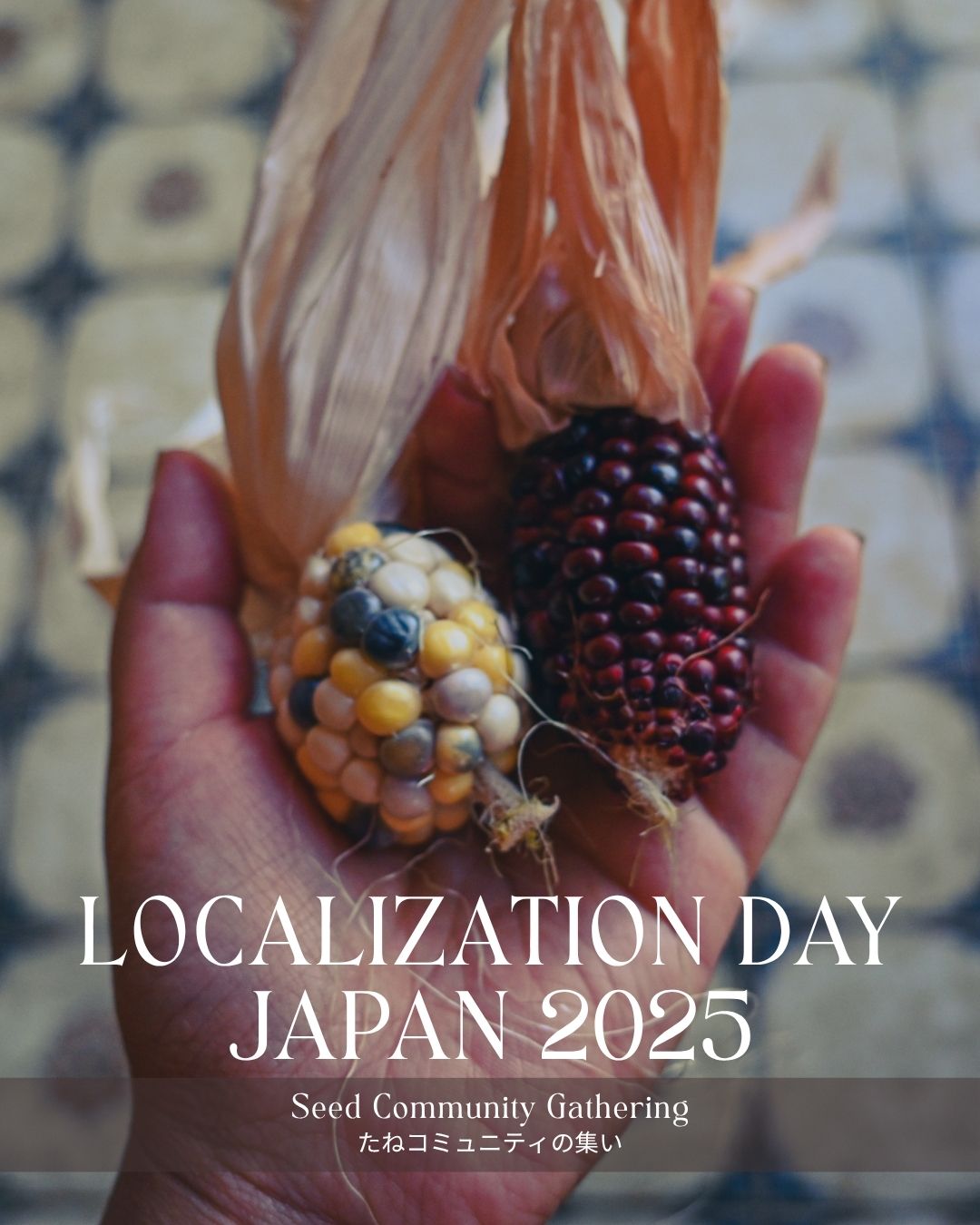 そうした多様性あふれる種を保全するための一番の方法は、ローカル(地域)ごとに、そこに住む人々の手で、蒔いて、育てて、食べて、共有して、生きたサイクルの中で風土に適応した種を継いでいくことだと思います。素朴な方法ですが、最も理にかなっていて、地球で一番長続きしてきた種継ぎのシステムです。
そうした多様性あふれる種を保全するための一番の方法は、ローカル(地域)ごとに、そこに住む人々の手で、蒔いて、育てて、食べて、共有して、生きたサイクルの中で風土に適応した種を継いでいくことだと思います。素朴な方法ですが、最も理にかなっていて、地球で一番長続きしてきた種継ぎのシステムです。
今回の「たねのローカリゼーション〜ゆるやかにつながる未来会議」で生まれたつながりはまだ芽吹き始めたばかりですが、これを今後どのように育んで行くことができるのか、今からとても楽しみです。
全国のタネと人とでゆるやかに繋がろう!
みんなでタネを蒔き、種と人、種を継ぐ人々をつなぐためのプラットフォームを一緒に育てていきましょう!ご参加をお待ちしております。
つながる方法は以下!
①\Instagramをフォローする!/
◆seedcommunity_japan
https://www.instagram.com/seedcommunity_japan/
◆OKシードプロジェクト
https://www.instagram.com/okseed.project/
◆たねの行進
https://www.instagram.com/seedsmarch/
②\たねマップに登録する!/
シードバンクやシードライブラリーなどたねの拠点として活動している方はぜひ「タネマップ」に登録してください!
◎ 国際シードライブラリーネットワーク
https://www.seedlibrarynetwork.org/explore-the-map.html?lang=ja
◆登録はコチラ( 世界のシードライブラリー/シードバンクのマップ作成に向けたアンケート)
https://forms.gle/52WT3ZhbJuar9Mbi9
③\たねの仲間になる!/
たねの仲間のプラットフォーム化を目指しています。日本のたねのコミュニティとして、全国でつながって輪を広げましょう!
◆「ゆるやかにつながるたねのなかま」登録フォーム
https://forms.gle/7djCJDq3cdE85zpJ7