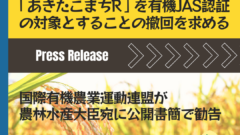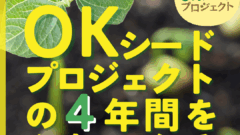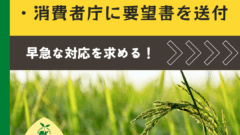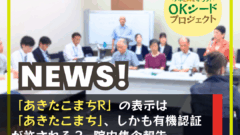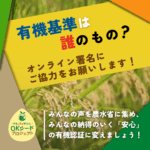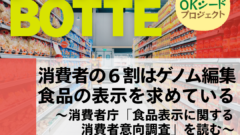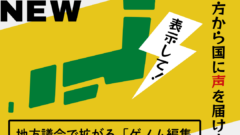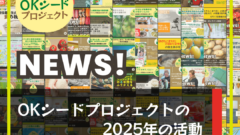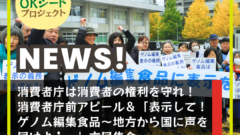重イオンビーム放射線育種による「あきたこまちR」に関して、よくある質問に対する回答をまとめました。
- 放射線育種って何?
- 放射線育種は長い歴史があり、世界各地で行われてきたと聞いたけれども、本当?
- 放射線育種は自然のプロセスを加速させるだけだと聞いたけど本当?
- 「あきたこまちR」は放射線育種ではないと聞いたけど本当?
- 「あきたこまちR」は遺伝子組み換えなの?
- 「あきたこまちR」は自然と同じで、安全というけど本当?
- 「あきたこまちR」は特許がかかっていて、自家採種禁止って本当?
- 秋田県だけの問題なの?
- 「あきたこまちR」や「コシヒカリ環1号」はなぜ作られたの?
- 秋田県はどうして「あきたこまち」を「あきたこまちR」に全量転換しようとしているの?
- もし「あきたこまちR」を栽培して収穫が激減したら誰が責任を取るの?
- 秋田県は従来の「あきたこまち」を栽培してもいいと言っているのだからいいのでは?
- 「あきたこまち」が好きで食べ続けたいのだけど、「あきたこまちR」と区別するためにはどうしたらいいの?
- 有機認証された「あきたこまち」であれば安心できるでしょ?
- この問題をコンパクトにまとめたものはありませんか?
1. 放射線育種って何? 目次に戻る
「育種」とは新品種を育成(作出、開発)すること。一般に品種改良と呼ばれています。「品種」とは、植物分類学の用語ではなく、園芸・農業の用語です。植物の姿・形の特徴、味や食感、栽培上の特徴など、「形質」「特性」等の違いで区別されます。現在の多種多様な作物は、それぞれ原産地で栽培されていたものが各地に伝わり、その地域の気候などの諸条件の下で栽培しやすいように人々が農耕する(タネを播き、栽培してタネを採り、それをまた播いて栽培を続ける)中で意識する・しないにかかわらず、改良を重ねてきた成果です。
人の手による交配(交雑法)(掛け合わせ)が行われるようになったのは、メンデルが修道院の庭でエンドウ豆の交雑実験をしてメンデルの遺伝法則を著わし(1865年)、その後、これが公に評価された1900年の「メンデルの法則の再発見」によって遺伝の法則が専門家のあいだに伝わってからのことです。1900年は日本では明治33年、すでに交雑法は行われていましたが、遺伝法則がわかった後は、めざましい発展をとげ、栽培作物の品種の多様性の源泉となっています。交雑法は、今日においても育種方法の主流です。
このような品種改良は、現代の科学の発達、とりわけ遺伝学、分子生物学、遺伝子工学等で遺伝子の構造や働きがわかってくると、「選抜」も自然界での突然変異を利用した品種改良も、いずれも植物のもつ遺伝子配列の総体(ゲノム)が部分的に変異を起こしていることが品種の形質・特性を変化させることがわかってきました。
「放射線育種」は、電離作用(イオン化)をもつ電離放射線(一般に放射線と呼ぶ)は透過性があり、生物を通り抜ける際に細胞内の遺伝子を損傷させる性質を持つことに着目し、種子・作物体に放射線を照射して人為突然変異を誘発させて、その遺伝子の変異を利用して新品種に育成する技術です。放射線照射を利用して遺伝子を改変させる点で、伝統的な自然界でおきる自然突然変異を活用した選抜、交雑法とは一線を画する新品種の開発手法といえるでしょう。
日本政府は原子力政策の下で1950年代末から放射線の農業利用を進めてきましたが、放射線育種では、放射性物質コバルト60が発するガンマ線を使ってきました。放射線育種のためのガンマールームは1956年に、1960年には屋外放射線育種場(ガンマーフィールド)が開設されました。ただし、こうしたガンマ線利用の放射線育種は2022年度までで終了しています。
今回問題となっている放射線育種はこれまで使われてきたガンマ線による放射線ではなく、加速器という装置により発生させる重イオンビームが使われています。しかし、この技術による放射線育種品種を開発した国は、IAEAのデータでは実質的に日本と中国のみとなっており、歴史的にも浅いものとなっています。日本では中性子線を使った放射線育種も民間企業によって始められていますが、現在のところ、この技術は、世界では研究に限られ、実用に利用しているのは日本だけのようです。
参考:放射線育種場および放射線育種(原子力委員会)
中性子線育種:「世界初の社会実装」 (株式会社クォンタムフラワーズ&フーズ)
2. 放射線育種は長い歴史があり、世界各地で行われてきたと聞いたけれども、本当? 目次に戻る
ガンマ線を使った放射線育種が第2次世界大戦後、世界で使われてきたことは事実ですが、効率の悪さと施設の維持の困難さゆえ、世界では基本的に終わっており、アジア諸国に一部残るだけとなっています。一方、「あきたこまちR」の祖先に当たる「コシヒカリ環1号」開発に使われた重イオンビーム放射線育種は歴史においても実績においても成果に乏しく、利用国は世界に広がってもいません。
ガンマ線による放射線育種は第二次世界大戦後まもなく「原子力技術の平和利用」の名の下で放射線技術の農業利用としてIAEA(国際原子力機関)がFAO(世界食料農業機関)と連携して世界各地で進められ、3000を超す品種が世界で開発されました。もっとも核技術の中核にあった米国では放射線育種は軍による軍事目的の実験に留まり、本格的な品種改良には使われませんでした。
世界でもっとも放射線育種を行ったのは中国、日本、インドの順となっています。しかし、この技術は施設維持に資金がかかるわりに効率が低く、世界におけるガンマ線放射線育種場は姿を消しています。日本でも2018年にガンマフィールド、2022年にガンマルームでの受付けが終了となりました。ガンマ線放射線育種はすでに利用が終わった技術と言えます。
一方、「あきたこまちR」の親である「コシヒカリ環1号」の育種に使われたのは重イオンビーム放射線育種です。サイクロトロンなどの加速器を使って種子にビーム状にした粒子を当てて遺伝子に損傷を与えて人為突然変異を誘発させ、それを品種育成に使う技術です。
重イオンビーム放射線育種の実施国はきわめて限られており、国際原子力機関(IAEA)のデータによると中国と日本のみです(この他にマレーシアとバングラデシュがありますが、どちらも日本で行ったものと考えられます)。IAEAのデータでは中国による最後の重イオンビーム放射線育種品種は1998年となっており、現在行っている国は日本くらいで、その日本でも実績はまだ限られた品種に留まっており、品種改良に広く使われたという実績は存在しません。
日本政府は、重イオンビーム放射線育種をアジア各国に拡げようとしていますが、効果を上げているとはいえず、世界に広がっていないのが現実です。
参考:ガンマーフィールドでの照射業務は2018年に終了 第4期中⻑期⽬標期間に係る業務の実績に関する評価書(案) (財務省・農水省)
ガンマールームは2022年12月28日に受付終了 お知らせ 放射線育種場ガンマールーム(ガンマ線屋内照射室)の照射業務の終了に伴う依頼照射の受け入れ終了について (農研機構)
Mutant Variety Database(国際原子力機関、IAEA)
3. 放射線育種は自然のプロセスを加速させるだけだと聞いたけど本当? 目次に戻る
近年、進化のプロセスに関する研究は大きく進みました。以前は自然放射線を受けて、遺伝子が突然変異することが進化の動力のように考えられた時代もありますが、実際には自然放射線による遺伝子の変異はほとんどが修復されていることがわかっています。実際の進化のメカニズムはもっと精妙で、環境への適応などのために生命自身が遺伝子の発現を調整する経験がエピジェネティックな遺伝として蓄積されていくこととも関連があることがわかってきました。自然界に存在する自然放射線よりはるかに強い放射線を当てて遺伝子を改変させる放射線育種はむしろその進化のメカニズムを損なう可能性があります。
また、宇宙線として粒子線は存在しても、大気によって大幅に吸収されてほとんど地上には届かないので、加速器を使って作り出すような重イオンビームによる突然変異が自然界でも起こりうるというのは根拠が乏しいと言わざるをえません。
4. 「あきたこまちR」は放射線育種ではないと聞いたけど本当? 目次に戻る
「あきたこまちR」は重イオンビーム放射線育種によって作られた「コシヒカリ環1号」を父方に、従来品種の「あきたこまち」を母方の親として、7回ほど母方との交配を繰り返して(戻し交配)作られた品種(後代交配種)です。
何度も交配を繰り返していますが、そこから生まれたもののうち、重イオンビーム放射線によって破壊された遺伝子(OsNramp5)が欠失しているものだけを選抜したものなので、「コシヒカリ環1号」と「あきたこまちR」は同様の性質(カドミウム低吸収性)を有する品種です。
つまり、「あきたこまちR」は、重イオンビーム放射線育種の品種「コシヒカリ環1号」の後代交配種であり、重イオンビーム放射線育種由来の品種であると言えます。
もし、「あきたこまちR」は放射線育種ではない、と呼ぶならば、祖先の代で遺伝子が改変(欠失)して失った機能(カドミウム、本来はマンガンをイネに吸収する能力)は、どこで付与されたのでしょうか。放射線育種由来であることを消すことはできません。
また、このような後代交配種は放射線育種由来ではないという理屈を適用すれば、ゲノム編集トマトはゲノム編集ではなくなります。というのもゲノム編集トマトとして売られているトマトそのものにはゲノム編集はされていないからです。ゲノム編集をするためにCRISPR-Cas9などを挿入して、遺伝子の一部を破壊しますが、そうしてできたトマトは挿入した遺伝子が入ったままで、この状態では遺伝子組み換えトマトという扱いになります。その規制を逃れるために、ゲノム編集をした後、ゲノム編集していないトマトと交配して、挿入した遺伝子の入っていないものを選ぶことで遺伝子組み換えでない、として作られたのがゲノム編集トマトです。通常品種と交配させた品種は交配品種であって、ゲノム編集ではないとしたら、ゲノム編集食品はすべてゲノム編集食品ではない、というおかしな話になってしまいます。
普通の品種と交配させたら、その過去が、どんな遺伝子操作したものであっても、取り消せるのであれば、操作し放題となってしまい、遺伝子組み換え食品の規制も実質的に無効にされてしまうでしょう。それは法的にも問題があり、許容することはできません。
「あきたこまちR」は「コシヒカリ環1号」育種の際の重イオンビーム放射線育種による特徴を引き継いだものですので、重イオンビーム放射線育種品種として扱う必要があります。
5. 「あきたこまちR」は遺伝子組み換えなの? 目次に戻る
遺伝子組み換えと呼ばれるものには外来の遺伝子を挿入して新たな品種を作る第一世代の遺伝子組み換え(組換えDNA技術)と、外来の生命の遺伝子(RNA)に由来するものを挿入して、遺伝子を操作する第二世代の遺伝子組み換えである「ゲノム編集」があります。「あきたこまちR」の元となった「コシヒカリ環1号」で使われた方法はこの2つの方法とは異なる重イオンビームを照射して遺伝子を改変させる放射線育種です。
ですので、「あきたこまちR」や「コシヒカリ環1号」は遺伝子組み換えとは違います。重イオンビーム放射線によってイネの中に本来あった遺伝子の一部の塩基(OsNramp5)が欠損しています。これはゲノム編集により特定の遺伝子を破壊することと同様のことが行われているため、遺伝子が改変された品種という点で、ゲノム編集食品と同様にその安全性をしっかり調査する必要があります。
6. 「あきたこまちR」は自然と同じで、安全というけど本当? 目次に戻る
重イオンビーム放射線育種によって作られた品種による食品が安全であるかどうか、という実証はされていません。重イオンビーム放射線育種は自然界で起きる遺伝子の突然変異と同じで安全だ、という理屈で検証されていないのです。そうした言い分は以下のような三段論法からなります。
- 自然の中で起きる突然変異でも遺伝子が欠損する植物が生まれることがある。
- 「あきたこまちR」や「コシヒカリ環1号」は重イオンビームによって遺伝子を欠損させた品種だ。
- だから、自然の中で起きた突然変異による品種も重イオンビームによる突然変異が生じた「コシヒカリ環1号」、「あきたこまちR」なども同じく遺伝子を欠損しているだけなので、自然のものと同じように安全だ。
しかし、重イオンビーム放射線育種による遺伝子破壊と自然界の中における遺伝子の欠損とはメカニズムが大きく異なり、同じと見なすことはできません。ですので、自然界に存在しない重イオンビーム放射線を使った影響が自然界で起きることとみなすこともできず、自然の変異と同じとは断定できません。そのため、実験もなしに安全とみなすことはできません。
それに加え、「あきたこまちR」や「コシヒカリ環1号」は遺伝子の一部が壊されているため、マンガンを吸う能力が3分の1未満になってしまっていることがわかっています。マンガンはイネの成長にとって、不可欠な必須ミネラルで、光合成や病虫害と闘うためのファイトケミカルを作る上で鍵となる役割を果たします。そのため、それが不足している水田で栽培した場合は、ごま葉枯れ病などの菌病にかかりやすくなります。その結果、農薬の使用が増えることが懸念されます。
また、マンガンが低い水田で、特に出穂期の高温が続くと収穫が大幅に激減してしまう可能性があります。そのような品種に全量転換することは食料不足にもつながりかねません。
マンガンはヒトやさまざまな生命にとっても不可欠なミネラルですが、過剰摂取すれば毒となります。マンガン不足が気になるとして、マンガンを水田に過剰に入れてしまえば、環境にも悪影響を与えることが懸念されます。
参考:コシヒカリ環1号のイネごま葉枯病発生リスクの評価および温室効果ガス発生・重金属吸収のトレードオフ関係解明、(1)イネごま葉枯れ病の発病リスクの評価 (農水省・アグリリサーチャー)
Mutation at Different Sites of Metal Transporter Gene OsNramp5 Affects Cd Accumulation and Related Agronomic Traits in Rice (Frontiers)
Characterizing the role of rice NRAMP5 in Manganese, Iron and Cadmium Transport (Nature)
OsNramp5基因变异影响水稻重要农艺性状的研究进展 (中国水稻科学)
7. 「あきたこまちR」は特許がかかっていて、自家採種禁止って本当? 目次に戻る
元の「あきたこまち」は自由に自家採種できる一般品種ですが、「あきたこまちR」の親となった「コシヒカリ環1号」は農研機構が種苗法上の品種登録をし、さらに特許を保有しており、その自家採種は不可となっています。「あきたこまちR」は秋田県が品種登録出願中ですが、「あきたこまちR」を自家採種することは育成者権者である秋田県が不可としています。「あきたこまちR」は農研機構の特許を使っているため、その種籾の価格にその特許料分が含まれます。
参考:農業環境技術研究所 保有特許情報 カドミウム吸収制御遺伝子、タンパク質及びカドミウム吸収抑制イネ
8. 秋田県だけの問題なの? 目次に戻る
いいえ、農水省は2018年に低カドミウム吸収米を今後の日本の主要な品種にする指針を作っており、すでに「コシヒカリ環1号」を親とする202系統もの品種開発が全国で進んでいます。秋田県だけでなく、九州や西日本を含めて、東北から九州までがその対象となっています。農水省は2025年までに3割、2030年までに5割の地方自治体がこの指針を受け入れることを目標に予算を組んで、進めています。さらに2024年には、農林水産省はヒ素対策を加えた「コメ中のカドミウムとヒ素低減のための実施指針」として改訂して推進しています。
「あきたこまち」は全国31府県で生産されていますが、「あきたこまちR」の生産を登録している県は秋田県のみであり、2025年から「あきたこまちR」の生産に切り替わるのは秋田県のみと考えられます(秋田県に「あきたこまち」の種籾を委託してきた地域では、他の県に種籾を委託するのか、それとも他の品種に変更になるのか、どちらかになると考えられます)。
従来の「あきたこまち」なのか、それとも「あきたこまちR」なのか、混在することになりますが、秋田県は「あきたこまちR」を販売する時には品種名ではなく、「産地品種銘柄」としての名称「あきたこまち」と表示して販売するとしており、このままでは区別がつかない状態になってしまいます。
「あきたこまち」は日本を代表する品種であり、全国のスーパーでも売られており、学校給食にも使われています。ですので、この問題は全国の人が関心を持つ必要があります。
参考:令和7年度予算概算要求額:⽔稲におけるカドミウム及びヒ素濃度低減技術の実証・普及(農水省)
令和6年度予算概算要求額:⽔稲におけるカドミウム及びヒ素濃度低減技術の実証・普及(農水省)
9. 「あきたこまちR」や「コシヒカリ環1号」はなぜ作られたの? 目次に戻る
鉱山・鉱山跡地や工場跡地から排出されたカドミウムによる土壌汚染が日本各地に極地的に存在しており、「コシヒカリ環1号」は、その汚染地でカドミウムを吸いにくい品種として開発されました。カドミウムを0.4ppm以上含むカドミウム汚染米は、地方自治体によって買い上げが行われており、汚染米は市場には出ていないとされています。汚染米の割合は天候によって大きく左右されますが、全国で数パーセント程度と考えられます。
農地の土壌汚染をなくしていくことが根本的に重要ですが、カドミウム低吸収性のイネを導入すれば、土壌に汚染があっても大丈夫、ということになって、土壌汚染対策が後退しかねません。化学肥料や土壌改良剤、下水汚泥肥料などにもカドミウムは含まれており、それらを使って農業を進めれば、農地のカドミウム汚染はむしろ悪化する可能性があります。またカドミウムの摂取経路で、お米は4割を占めるに過ぎず、土壌汚染をなくさない限り、他の経路から人体が汚染されてしまう可能性があります。
ですので、環境を汚染させない、汚染された土壌から汚染をなくすという総合的な政策が不可欠で、お米にカドミウムが含まれていなければいい、というのは短絡的な考えと言わざるをえません。実際に世界ではカドミウム対策としてさまざまな方法が試されており、お米に遺伝子操作する以外にも有望な対処方法は提案されていますので、そうした方法を活用することが望まれます。
小手先の技術ではなく、地域から汚染をなくす(隔離する)総合的・長期的政策と施策が必要です。
参考:コメ中のカドミウム低減のための実施指針 (農水省消費・安全局)
「コメ中のカドミウムとヒ素低減のための実施指針」(農林水産省)
10. 秋田県はどうして「あきたこまち」を「あきたこまちR」に全量転換しようとしているの? 目次に戻る
秋田県ではカドミウム汚染地域だけ「あきたこまちR」を作ったら、それが汚染地域のお米として認識されてしまうので、風評被害によって売れなくなる。また逆に、従来の「あきたこまち」が「あきたこまちR」といっしょにあると、それは「あきたこまちR」よりもカドミウムが高いと誤解されて、どちらも風評被害を受ける可能性があるので、すべて「あきたこまちR」にすると言っています。
しかし、同じ理屈で言うなら、秋田県だけで「コシヒカリ環1号」系品種である「あきたこまちR」を栽培するということは秋田県のお米に対する風評被害を不可避にしてしまうわけで、他の府県ではまだ生産していない時点で秋田県が全量転換してしまうというのはあまりに拙速だと言えるでしょう。
また秋田県では今後の重点品種である「サキホコレ」など県が提供する他の品種もすべて「コシヒカリ環1号」との交配を進め、100%カドミウム低吸収性の米に変えることを計画しています。
実際には、カドミウム汚染地域は限られており、まったく必要もない地域に「あきたこまちR」などの重イオンビーム放射線育種米を押しつけることになります。
11. もし「あきたこまちR」を栽培して収穫が激減したら誰が責任を取るの? 目次に戻る
「コシヒカリ環1号」や「あきたこまちR」でカドミウムを吸収する遺伝子OsNramp5を破壊した品種はマンガン吸収能力が落ちるため、マンガンが低い水田で出穂期に高温が続くと、収穫が激減する可能性が指摘されています。マンガンは光合成に不可欠なミネラルで、その不足は成長にも大きな影響を与える可能性があります。
しかし、農水省は、マンガンを補う必要があることについては、すでに栽培マニュアルで注意喚起しているとのことで、収穫が激減したら、それは農家のやり方に問題があるということで、農家の自己責任であるとして、責任を取ることはないと言っています。
農水省のマニュアルでは、マンガン不足の水田にはマンガンを足す必要があると指導していますが、農家が持つ水田の一つ一つにどれだけマンガンが含まれているか、農家に知る手段が確保されているでしょうか? マンガン肥料を施す費用は県が負担してくれるでしょうか? 従来の品種であれば不要であった農家の負担を新たに増やした上に、収穫が減った場合は農家の自己責任とするのは理不尽な話であり、県や農研機構・農水省は責任があると言わざるを得ないのではないでしょうか?
参考:コシヒカリ環1号のイネごま葉枯病発生リスクの評価および温室効果ガス発生・重金属吸収のトレードオフ関係解明、(1)イネごま葉枯れ病の発病リスクの評価 (農水省・アグリリサーチャー)
Mutation at Different Sites of Metal Transporter Gene OsNramp5 Affects Cd Accumulation and Related Agronomic Traits in Rice (Frontiers)
Characterizing the role of rice NRAMP5 in Manganese, Iron and Cadmium Transport (Nature)
OsNramp5基因变异影响水稻重要农艺性状的研究进展 (中国水稻科学)
12. 秋田県は従来の「あきたこまち」を栽培してもいいと言っているのだからいいのでは? 目次に戻る
秋田県は従来の「あきたこまち」の種籾(種子)は2025年以降は提供しないと言っています。ですが、農家が独自に他県から種籾を確保したり、「あきたこまち」は自家採種できるイネなので、自家採種したりすることで種籾を確保すれば従来の「あきたこまち」は栽培できるとしています。
しかし、これまで種籾をJAなどから入手していた農家にとっては種籾の確保が難しくなります。他県から購入すると、値段が上がったり、多くの手間がかかります。
そして、種籾が確保できたとしても、問題は終わりません。収穫・集荷・出荷まですべて自力でやっている農家の場合は大丈夫ですが、農協などに委託している場合、その農協が「あきたこまちR」のみを扱うのであれば、せっかく苦労して従来の「あきたこまち」を作っても従来の「あきたこまち」として売ることができなくなってしまいます。
生産者が自分で産直ルートまで持っている農家でもない限り、従来の「あきたこまち」を生産することは大変な困難があると言えます。
このような不利益を公的事業として行われている種籾の生産において、県が農家に与えることは不当です。これまで通り、流通経路も含めて確保できるように県の責任で関係業者に呼びかけるべきであり、それもせずに、従来の「あきたこまち」を農家は栽培しようと思えば、栽培できるのだから県の対応は問題ない、というのは県が地方自治体として果たすべき役割を放棄しているといわざるをえません。従来通りの「あきたこまち」の種籾の提供を含め、出荷体制まで含めて、秋田県は従来の「あきたこまち」の農家支援を再開することが必要です。
13. 「あきたこまち」が好きで食べ続けたいのだけど、「あきたこまちR」と区別するためにはどうしたらいいの? 目次に戻る
秋田県によると、「あきたこまちR」はお店では「あきたこまち」としてしか表示しなくていいとしています。つまり、スーパーなどでは消費者はそれが「あきたこまちR」なのか、「あきたこまち」なのか知る術がないことになります。
そこで、このような表示はおかしい、「あきたこまちR」か「あきたこまち」か消費者が見分けられるように是正させるよう消費者庁に要請しています。
秋田県においても、従来の「あきたこまち」の生産を続けようとしている農家の方がいます。直接、そうした農家と組んで、産直をすることも「あきたこまち」を守る上で重要な方法になっていくでしょう。
また、現状では重イオンビーム放射線育種米に表示義務がありません。他方、重イオンビーム放射線育種の米ではないと明記することは禁止されていません。たとえば、「これは従来のあきたこまちです(重イオンビーム放射線育種ではない)」という表示をして販売することは可能です。
流通業者の方たちとも協力して、地域のお米屋さんで、従来の「あきたこまち」であることをはっきりと明示して売れるようにできないか、模索しています。
14. 有機認証された「あきたこまち」であれば安心できるでしょ? 目次に戻る
いいえ。農水省は「あきたこまちR」でも有機認証できるという立場をとっています。秋田県も、農水省が認めているからと、有機認証できると断言しています。だから、2025年産米以降、有機認証された「秋田県産あきたこまち」を買っても、そのほとんどは「あきたこまちR」である可能性を否定できません(*なお、秋田県産以外は従来品種です)。
農水省は、2024年7月には、日本の公式の有機基準である「有機農産物JAS」(JASはJapanese Agricultural Standard、日本農林規格)等の「Q&A」に問10-10を追加新設して、「放射線照射を利用して品種改良された品種やこれらを祖先に持つ品種の種苗」を使った農産物を「有機」「オーガニック」であると有機認証しても「問題ありません」という見解を公表しました。
しかし、この見解は、これまで長年にわたり使用されてきたガンマ線使用による品種改良(新品種の開発、品種育成、育種)の種苗も一部で有機認証されてきたという既成事実によるものです。これを重イオンビーム使用により開発された「コシヒカリ環1号」や「あきたこまちR」の取扱いに当てはめることには無理があります。
日本でも世界でも、「重イオンビーム育種」(育種とは、新品種を育成すること)を使った米を主流の生産物にするという大々的な実用化はこれまで例がありません。
重イオンビームは、ガンマ線使用に比べ、単に突然変異を誘発する確率が格段に高まるというだけでなく、種子の遺伝子に及ぼす作用も異なります。ガンマ線の場合は細胞内の水分子を電離させることで活性酸素が発生し、遺伝子を損傷して突然変異を間接的に誘発させますが、重イオンビームは粒子線が遺伝子DNAの二本鎖を直接に破壊・損傷させて突然変異を誘発させます(河田昌東「『あきたこまちR』の何が問題か―科学的解説」)。
なぜ、農水省は重イオンビーム育種で作った品種を有機認証できると言うのでしょうか。それは、整合性をとるべき有機基準の国際標準となっているコーデックス有機ガイドライン(FAO/WHO合同食品規格委員会)にガンマ線や重イオンビームを使って品種開発をしてはいけないと明記されていないので禁止技術ではないと解釈しているからです。
しかし、コーデックス有機ガイドラインを子細にみれば、「遺伝子操作技術/遺伝子組換え生物」を生産・加工基準の「適用の範囲」から「除外」して禁止技術としています。それと同じ理由で放射線を使用する品種開発も禁止技術に相当することが読み取れるはずです。
つまり、自然の摂理を尊重する有機農業の原則に照らせば、有機生産で使用する品種改良の方法は、歴史的、伝統的に行われてきた品種改良、つまり、農耕と共にある採種過程での「選抜」、メンデルの遺伝法則の発見以降に品種改良の主流となっている「交雑法」、そして自然界における突然変異を新品種に育成していく自然突然変異の利用に限るということです。
有機基準では、自然界で自然に起こる自然突然変異と、人為的に放射線を照射して人為突然変異を誘発させることを峻別しています。重イオンビーム使用の場合、DNAの二本鎖が同時に破壊・損傷されますが、そのようなことは自然界ではほとんど起こらないといわれています。そもそも、生物(生命)の設計図とも根幹とも言われる遺伝子配列「ゲノム」を人為的な操作により改変させてよいのか、という生命倫理こそが問われることになります。
人為的な技術介入で本来の「ゲノム」を改変させる「ゲノム編集技術」も、コーデックス有機ガイドラインに禁止技術として明記されてはいませんが、「新しいゲノム技術(New Genomic Technologies)として有機基準で禁止していくというのが、世界の動向です。ゲノム解析等の発展で結果として特定の遺伝子の欠失を確定できるようになっているので重イオンビーム育種も、ゲノム編集技術と同じように、禁止技術とすべきです。
重イオンビーム育種を現在使っているのは日本くらい。それを日本の有機認証で認めてしまったら、日本の有機食品への信用が墜ちてしまうでしょう。農水省の見解は有機食品を買う消費者の考えとは大きく食い違うものではないでしょうか? 有機基準とは、「有機」「オーガニック」を求める消費者と生産者が納得して初めて意味を持ちうるものです。
重イオンビーム育種由来の「あきたこまちR」の有機認証を消費者は認めないという声を上げていき、農水省に見解の変更を求めましょう。
15. この問題をコンパクトにまとめたものはありませんか? 目次に戻る
この問題をA4版表裏にコンパクトにまとめたチラシを作りました。PDF形式でダウンロードできます。ご自由に印刷するなどして、ご活用ください。重イオンビーム放射線育種米「あきたこまちR」なにが問題?チラシができました!
最新投稿記事
もっと見る