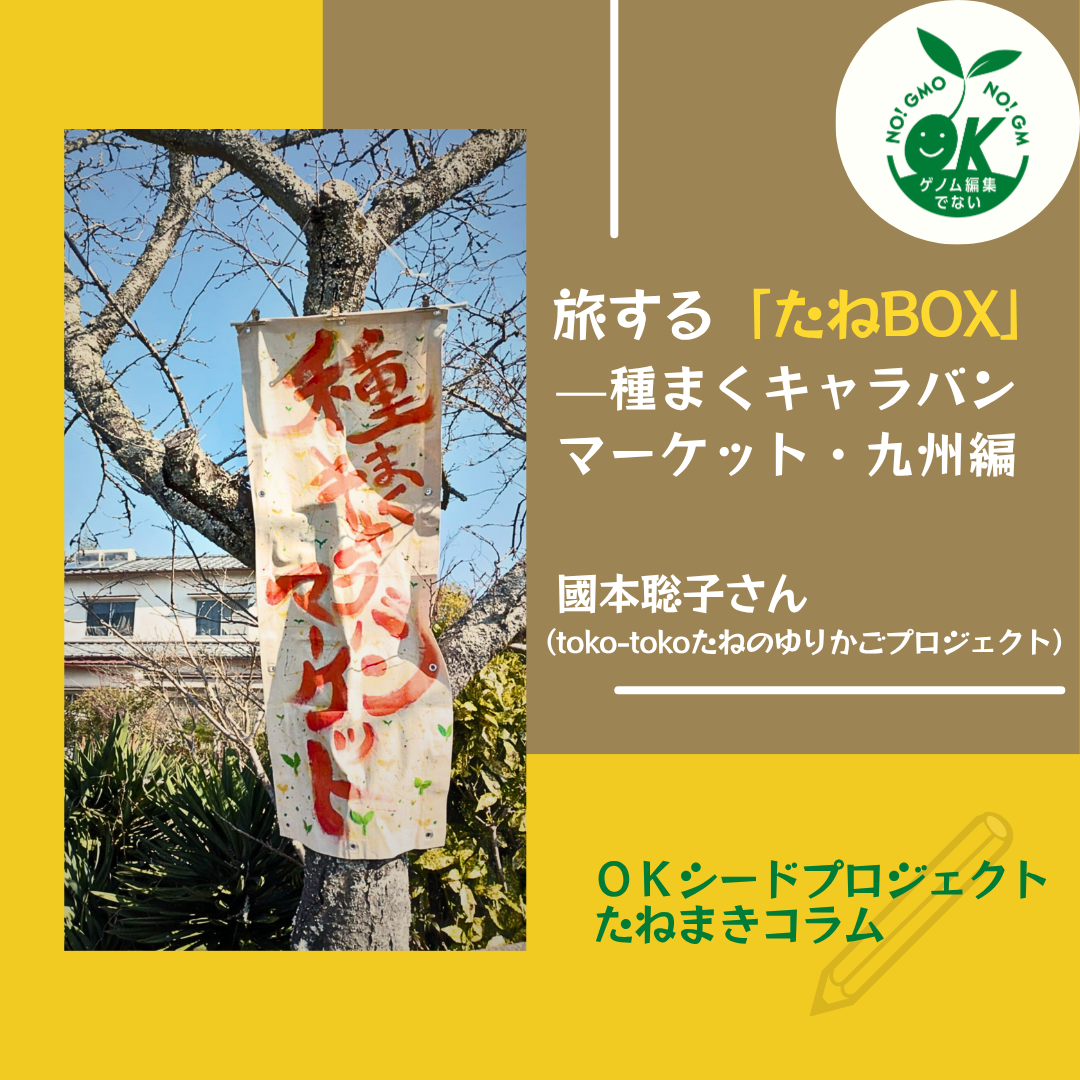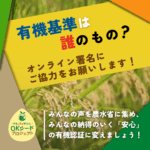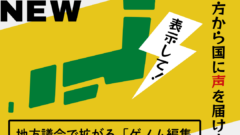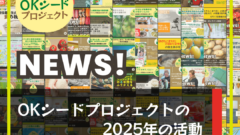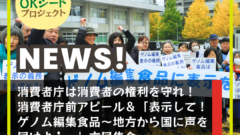OKシードプロジェクトはこの7月で開始から5年目を迎え、この間、全国のさまざまな団体や農家、食品店や食に関わる卸業者、飲食店、そしてたくさんの個人のみなさんが、わたしたちの活動に関わってくださっています。みなさん、いつも本当にありがとうございます。
今回のたねまきコラムは、開始当初から活動を共にしてくれている「北海道食といのちの会」の活動をご紹介します。
OKシードプロジェクトが全国のみなさんと連帯して取り組んだ「ゲノム編集トマト苗配布問題」では、北海道食といのちの会にアクションを牽引していただきました。取り組みのマニュアルや要望書のひな形を他の地域へも提供していただいたことで、全国からたくさんの方、特に子育て世代の方が参加しやすくなり、素晴らしい結果を残すことができました。
地域でタネを撒き続けるその精力的な活動は、北海道だけでなく全国に拡がっています。
北海道食といのちの会、事務局長の山﨑栄子さんからのレポートです。
5年目を迎える「北海道食といのちの会」
 安全安心な食べものと、それを持続的に生産する農業と地域社会にしたいと願って「北海道食といのちの会」を発足して、4年が経ちました。第5回総会を迎えるにあたり、この1年の活動を振り返り、お伝えしたいと思います。
安全安心な食べものと、それを持続的に生産する農業と地域社会にしたいと願って「北海道食といのちの会」を発足して、4年が経ちました。第5回総会を迎えるにあたり、この1年の活動を振り返り、お伝えしたいと思います。
当初から活動の柱を①遺伝子操作生物への対応、②危険な化学物質削減、③有機農業や自然栽培された食品の生産と消費の振興―として活動をすすめてきました。活動はグループ分けをして担当役員と参加したい会員でオンライン会議をしながら行っていますが、私の担当は「遺伝子操作生物への対応」です。会を立ち上げてすぐ、グループを作り、その中で話し込みを続けて「ゲノム編集トマト苗を受け取らないで」の活動をスタートさせました。それがOKシードプロジェクトや全国の意志ある方たちでも展開され、結果、小学校や福祉施設へゲノム編集トマト苗が届けられる動きがないことに安堵しています。少人数では対抗できなくても、全国の力を結集すれば対抗できる! 諦めなくてよかったと思いました。
ゲノム編集食品表示を求める意見書提出運動
次は、やはりゲノム編集食品に表示をする!ことを全国の方と共に進めていきたいと考えています。北海道には179市町村があり、少しでも多くの自治体議会から国へ意見書提出ができるよう、会としてできることを少しずつ行っています。まずは、この活動をすすめてみたい・興味があるという会員議員や出会った議員に呼びかけて、2025年5月「ゲノム編集表示意見書提出運動会合」をオンラインで行いました。道内の議員6人と遺伝子操作グループメンバー・役員も参加し、内容はすでに意見書提出をしている「北広島市」と「札幌市」の事例報告とそれぞれの議会の状況の意見交換をしました。
行ってみてわかったことは、やはり議会によってどうすれば意見書採択へこぎつけるかはさまざまであることでした。その中で会の役割はどうしたらよいかを考えました。ちゃんとできるかどうかは横に置いて、全国の提出された意見書を分析して、これなら通りやすいという2~3くらいのパターンを提示できるようにして、意見交換の会合を繰り返し行っていこうと決めました。関心を持っている議員とつながって、ネットワークを大事にして「ゲノム編集食品(あるいは生物)に表示する」ことを目的に一致させて2025年度の活動にしていこうと思っています。
この後、会合に参加した「江別市」が6月の議会で意見書採択できたとの、嬉しい報告が届きました。当会の第5回総会の記念講演では、天笠啓祐さんに来ていただき「農薬とゲノム編集食品の不都合な真実」としてお話いただき、意見書提出の機運を盛り上げたいと思っています。合わせて、ケミカルグループ(化学物質削減)が取り組んでいる全道の小学校での農薬使用実態調査活動の動きもあり、天笠さんからアドバイスいただき進めていけたらと考えています。
持続可能な農業と地域社会をつくる「たねまきの日」
当会の前身といってもよい「北海道たねの会」が、以前行っていた「たねまきの日」を復活させたいと当初から話していたのですが、担当役員がいないため保留になっていました。2024年新役員となった伊藤一弘さんに担当をお願いできたため、継続して行えるようになりました。「たねまきの日」は会員同士の交流・学習を行いますが、持続的な農業と地域社会をつくるタネをまきたいとの願いを込めてこの名称をつけています。
3ヵ月に一度程度の開催を基本にし、これまでに4回の講演・上映会を実施しました。各回のテーマは、ネオニコチノイド系農薬と健康への影響、北海道産食材と読み物がセットになった情報誌に込められた生産者と編集者の想い、令和の米不足問題、大地再生農業(リジェネラブル農法)の映画上映と日本語版を製作された実践農家の講演を組み合わせて行いました。講演会は平日の夕方に行い、お腹が空いている時間帯のため、減農薬米で握った大きめのおにぎりを用意したところ大変好評でした。上映会+講演会は、土曜日の午後に行い、定員80名が満席となりました。
テーマ設定は、今学びたいことや北海道に視点をあてたことから考えて、講師は会員でお話できる方がたくさんいらっしゃるというのも企画しやすく、幅を広げられる要因になっていると思います。次回は、日本ジャーナリスト会議主催「コメ騒動と食料安保の行方」講演会(久田会長講演)に当会が協力という形で、「たねまきの日」として呼びかけ、11月には、有機農業を実践されている農家さんのお話を聞こうと計画しています。定期開催することで、企画進行と周知がスムーズになってきました。何より、参加した人たちが来てよかった!、学びやヒントをもらえたと思っていることが継続のチカラになっています。たねまきの日が、当会の活動の基盤になっていけたらよいなぁと思っています。
持続的な農業や地域社会をつくることは簡単ではないけれど、いろいろな人たちが楽しく食べたり、話したりしながら進めていけば可能性は広がると思っています。
(北海道食といのちの会 事務局長 山﨑栄子)