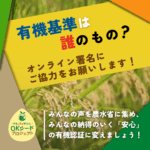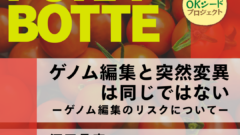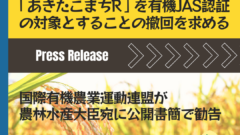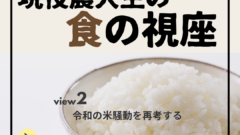ここまで、私の故郷宮津での思い出や大学時代に経験して身につけてきたことなどについて記述してきました。いよいよ、本題のリージョナルフィッシュ株式会社のことについて、なぜ、私が『ゲノム編集魚が良くない』と思うのか?について述べたいと思います。
本題に入る前に、沿岸漁業についての私の思いを述べておきます。
漁業は略奪的な産業か?
農業は土地を所有(あるいは借地=昔は小作=)したうえで、耕し、播種し、病害を防除したり、雑草を除去して作物の生長を促し、結実した物を収穫するという文字通りAgriculture(語源は畑を耕す=culturaはラテン語で文化を意味する=)です。お百姓が自分の管理下で(苦労して)作物を栽培し収穫し、種子を採取(このことが最重要だと考えています)して、季節になればまた、播種するということを繰り返すものです。
一方、漁業は海という公の場所(中世の網元制度は別として)で天賦の獲物(魚介類)を獲るという、本来、無主物である海の魚介類を獲ることを生業とする略奪型の産業であると私は捉えていました。確かに、沖合漁業や遠洋漁業では『資源管理』をしない限り略奪的だと思います。さらに、漁師は古老であればあるほど、ギャンブル的です。「自分が若いころにはこんなに大きい魚を釣りあげたことがあった」、「昔は魚が山ほど獲れて困ったくらいだ」という昔の自分にとっての幸福な経験を忘れらず、またいつの日かそのような経験ができるだろうと願って、日々海に出かけるという、一種のギャンブル中毒者のような面を持っていました。略奪的でギャンブル的、どちらにしてもよい響きの言葉ではありません。
ところが、就職して、広島市の水産振興計画の策定に携わった際に、クロダイの増殖を主眼としたものでしたが、クロダイの稚魚を放流するだけではなく、元来、広島市に存在した干潟や藻場を保全することの重要性に気づかされたのです。すなわち、沿岸漁業は海からの賜物を得るために漁師は海の本来の生産力を保持するために、海の環境保全に貢献しているのです。たとえば、古くから『魚付き林』といって、海岸近くに木を植えて海に影を作り出して魚の隠れ家にしたり、林野から海に流出する栄養分で海の生産力を高める効果を知っていたのです。現在は森林法で『魚付き保安林』として伐採や開発が厳しく制限されています。
また、築磯(つきいそ)といって、海に岩石を投入します。これは海底を凹凸に富んだ複雑な地形にして稚魚の育成場にしたり、柴を投入して魚を蝟集したり、また、岩石中に含まれる成分(酸化第二鉄)が水中に溶け出すことによって、海藻の生育に効果があるといわれます。このように、古くから自分たちの漁場を守り造成してきたのです。それを考えると、沿岸漁業者は『略奪者』ではなく、沿岸の環境保護活動をしていたといえるのです。
農業も同じで、水田が減り『天然のダム』が減少したことで、近年のゲリラ豪雨によって水害が頻発している。農業の衰退が災害までをもたらしているといえるでしょう。
漁業も農業もこのような意味で、環境保全型産業であると同時に、災害に対しても一定の予防効果を持った重要な産業であると考えます。
会社は社会的存在である
さて、リージョナルフィッシュ社という会社について私の所感です。私は2024年8月まで、福岡の小さな会社で常務取締役として会社の経営に携わってきました。その経験から、会社というものについて少し私見をお話しておきたいと思います。
・社会的存在であること
あたりまえのことですが、会社は人格(法人格)をもったものです。したがって、法に基づいた社会的な存在です。また、会社に求められることは、事業を営み、利益を上げて、利益を還元することです。最近は株主にばかり還元することが重視されますが、社員への還元も重要です。私がいた会社では株主は取締役だけでしたので、株主への還元は出資額に対して金利分程度を還元すればそれで十分で、利益が出た際には、社員に通常の賞与とは別に『決算賞与』として還元していました。もう1つ会社にとって重要なことは、社会の一員として税を納めることです。
ですから、会社にとって重要なことは『利益を上げる』ことです。
これらのことが、会社が社会的な存在であることを証することだと思います。
・コンプライアンス
いまの世の中でしばしば、コンプライアンスといわれます。狭義では『法令遵守』のことですが、通常はもっと広い意味で使われると思います。すなわち、世の中で法令を守ることは論を待ちませんが、それ以上に世の中の『規範』や、社会的倫理に基づくことです。これは、ハラスメントの防止やジェンダー平等の精神に基づく会社経営を行なうことが求められます。これらのことが、会社が社会的な存在であることを証することだと思います。
・SDGsに基づいた経営
会社は成長し続けるために不可欠なものは『持続可能に発展する社会』だといわれます。これらのことについては、一般社団法人SDGs経営推進協会(https://sdgs-blp.my.canva.site/)で確認できます。ここでも、会社の社会課題に取り組むことの必要性や、地域への貢献や環境への配慮を行なう経営が、会社の持続的発展に寄与するものといわれています。
また、SDGs経営は自分だけよければよいということを戒めた近江商人(伊藤忠商事の祖も近江商人)の『三方良し(買い手よし、売り手よし、世間良し)』とする言葉と同様で、自分(会社)の周囲に存在する人たちにもよいものでなければ、商売は続いていかないものだということです。
会社を持続的に発展させようと思えば、顧客からの評価も得て、自らも利益を上げられ、かつ、世間からも認められる必要があるということです。
ここまで述べてきたこととリージョナルフィッシュ社の立ち居振る舞いを比べてみて、みなさんはどのように感じられるでしょうか? 『宮津∞麦のね宙ふねっとワーク』によれば、リージョナルフィッシュ社は質問に対して『高圧的』で、『威圧的』で訴訟までちらつかせる始末のようです。会社として社会の一員足ろうとするならば、真摯な会話は当然のことだと思うのです。
例えば、
① 国(あるいはその外郭団体)から、多くの補助金を得ているにもかかわらず、さまざまな情報についてそのほとんどを公開することをしない。→社会の理解が得られるでしょうか?
② そもそも、企業として採算性はとれるのか? 補助金等の公金を注入したときに、それらは社会に還元できるのか? →少なくとも現在、ゲノム編集魚の販売により利益が上がっているとは考え難い。
③ゲノム編集魚を創出し、『養殖』する過程で、環境へ及ぼす影響や、海域の生態系への影響や、天然の魚類への遺伝的攪乱などの安全性は担保できるのか?→担保できるのであれば、その根拠を公開すべきではないでしょうか。
近江商人の『三方よし』と照らしてみると、何も『良い』ことはなさそうです。
食糧問題、タンパク質の供給の問題
リージョナルフィッシュ社のホームペイジを見ると、“2030年には『タンパク質クライシス』が起きて、タンパク質の需要は供給を上回る。”といい、また“日本の水産業は衰退の一途をたどっている。”そのため“より効率的な養殖業が求められて”おり、ゲノム編集をすることにより、品種改良の速度を30年要する期間を2〜3年で可能にするという技術が必要とされていると述べています。また、彼らが取り組む陸上養殖は『環境にもよい』と謳っています。
私は海辺の町で育ったので、魚食が大好きです。自分の摂ってきたタンパク質は魚介類が最も多いと思います。
品種改良の時間が極端に短縮される技術だといいますが、さまざまな環境(養殖環境についても)に適応できる(生きていける)品種改良は時間がかかるのは当然のことではないでしょうか? 短期間に品種改良された魚が継代生き続けられるのでしょうか? 私は大いに疑問を持っています。私には、ゲノム編集魚は見る限り、奇形魚にしか見えませんし、とても健康な魚には見えません。そんなモノを好んで口に入れる人がいるのでしょうか?
また、『環境によい』陸上養殖といっていますが、具体的にどのようなことを指しているのでしょうか? ぜひ、具体的にその内容を教えて(公開して)いただきたいものです。
私は前にも述べましたが、漁業は漁師が漁場としての海の環境を守り創出してきた『環境保全型産業』であると考えています。環境をよくするためにも、海からのタンパク供給を増やすためにも日本の沿岸漁業の再生と発展を真剣に考え、取り組む必要があるでしょう。そのためには、漁師が漁業で『食っていける』ような仕組みも構築し、後継者も育つようにする行政の施策展開が国のみでなく、地方自治体の段階でも必要です。
専門家・研究者は倫理に基づいて
私はゲノム編集という技術を全否定するものではありませんが、少なくとも生命科学の分野において、遺伝子操作に並んでゲノム編集は慎重に行なうべきものだと考えています。
これらの技術は直接的に生命にかかわるもので、これらの技術を用いれば『デザイナーズベイビー』への道まで開きかねないという懸念があり、人間の自然進化にまで手を加えかねないという重大な倫理上の問題があります。
少なくとも、来るタンパククライシスに備えて、魚からのタンパク供給を効率よくするためにゲノム編集魚を創出するということは『良くない』と思っています。
ゲノム編集魚を作り出しているリージョナルフィッシュ社の経営層、技術者・研究者はこのような倫理上の問題や懸念を議論しつくしたうえで、かつ、安全性も担保できることを確認して、『陸上養殖』を行なっているのでしょうか?
リージョナルフィッシュ社のウェブサイトをみると、高学歴で優秀な社員が在籍されているようです。彼らは、自分の持つ技術を発揮すればよいとだけ思うのではなく、自分の技術が重大な倫理上の問題を孕んでいることが自覚できているのでしょうか? また、彼らのような若くて優秀な技術者・研究者は自分の技術・研究成果を論文などで発表したいという研究的な健全な野心(功名心)を持っていると思います。野心だけではなく、自分の成果を世に知らしめて、議論してもらいさらに発展させたいという謙虚さでもあるかも知れません。いずれにせよ、外部へ出したいと思うのではないでしょうか? しかし、リージョナルフィッシュ社は情報公開には否定的な会社であり、論文などでの発表ができないということになれば、若い優秀な研究者は、辞めていくのではないかと思います。あるいは、『研究』は諦めて高額な報酬だけを期待して会社に残るということになるのでしょうか? 多国籍企業の『モンサント』の研究所に在籍していた私の大学の同期の友人から同じようなことを聞いたことがあります。
会社(企業)は人材によるものです。こういう面からも企業の永続性に私は疑問を感じます。
今後の展開
私はここまでのべてきましたように、リージョナルフィッシュ社が進めるゲノム編集魚はよくないと思っています。
・ゲノム編集魚は売れるのか
そもそも、筋肉だらけの、マダイには見えないゲノム編集マダイを見て「美味しそう」、「食べたい」と思う人がいるでしょうか? 外見からはとてもマダイ(Pagrus major)には見えません。奇形魚なのではないかと思うのではないでしょうか? 一般の鮮魚を見て魚を買って食べてきた人たちにとっては、マダイとは似ても似つかぬ魚です。これが市場で売れて利益が出せる代物とは思えません。企業的に成り立つのか大いに疑問です。
・リージョナルフィッシュ社へ投資する人たちの責務
いろんな情報を見聞きすると、リージョナルフィッシュ社に『出資』している企業があるようです。それも、国内の有名企業であるミツカン、セブン・イレブンや地方銀行(松山に本店がある『伊予銀行』)系の『いよぎんキャピタル』や、ゼネコンである『(株)奥村組』などです。彼らの出資により、リージョナルフィッシュ社は30億円を上回る資金調達をしたようで、すごい資金調達力があります。
奥村組のウェブサイトによれば、会社として企業行動規範として挙げた10項目のうちの4番目に『企業情報の開示=広く社会とのコミュニケーションを図り、企業情報を正確に開示する=』また、5番目に『社会貢献=地域社会との良好な関係の構築と維持に努め、豊かな社会の形成に貢献する=』を掲げています。奥村組は、自社で定めたこの行動規範に基づいて、投資家としての彼らは、リージョナルフィッシュ社に同様のことを要求すべきではないでしょうか。そうしなければ、自社の行動規範と整合しませんし、自社株主への『説明責任』も果たせないのではないかと思います。これらの投資している会社にリージョナルフィッシュ社の姿勢について尋ねてみてはどうでしょうか。
・専門家との連携
この問題に関する取り組みは、国会議員会館での院内集会を開くなど、さまざまな拡がりをみせるのだ思います。国会議員、地方議会議員などとの連携や協働も必要でしょう。それに加えて、専門家・学者・研究者との連携、協働が望まれると思います。リージョナルフィッシュ社が(農学系では発言力、影響力が強い)京都大学、近畿大学発のベンチャーであることから、農学系の専門家や研究者はさまざまなしがらみや圧力により、自由な意見を発しにくい状況があるかもしれません。しかし、私はこの問題はそれほど軽いことではないと思います。すでに大学を退官した元教官や研究者で、しがらみが少なくなった人たちが声を挙げられないものかと思います。また、それは各々の人の『思想・信条』が違ってもみなが共通して『良くない』と思えることではないでしょうか?
とりわけ、学会(学術団体)の果たす役割は大きいのではないかと思います。ゲノム編集そのものを全否定する必要はなく、この技術のメリットとデメリットに関する議論をする必要があるのではないでしょうか? そのなかで、ゲノム編集魚についても『良くない』ということを議論すべきでしょう。それは、水産学会、魚類学会や生態学会でしょう。
また、リージョナルフィッシュ社自らが『リージョナル(“地域の”という意味)』と標榜しています。言葉だけからみると、『地域』を重視する会社のようにみえますが、はたしてそうでしょうか。宮津のように過疎が進み、経済的にも力の落ちた地域で、さらに田舎で一部の為政者に対して市民が『モノが言いにくい』地域で、物事を進めようとすることに私は、その社名に、ある種『偽善』を感じます。このような地域での問題であるならば、地域経済学会(かつて公害問題では先駆的論陣をはった)による議論も期待されると思います。学会に望めないなら、心ある研究者の個々と連携して運動を拡げることも考えるべきではないでしょうか。まだまだ、このことを知らない人が多いのです。知れば、ゲノム編集魚の姿を見れば、誰もが『思想・信条』を超えて声を上げるでしょう。
稿を閉じるにあたり、リージョナルフィッシュ社のゲノム編集魚の『技術』が現在、私の住むタイに『輸出』されそうになっているという報に接し、とても困っています。タイは熱帯であるだけに生物生産のポテンシャルがとても高い国(地域)です。ゲノム編集した魚で促成栽培的に魚を生産する必要などまったくないと思います。野菜も年中通して収穫できるし、お米(インディカ米)はとても美味しいし安い。日本に住んでいることが嫌になって、タイに移住したのに、このタイでそんな『よくない』ことを目の当たりにしたくないのです。美味しいタイ料理を食べて平穏に暮らしたいのです。
この望みを叶えるためにも、みなさんの今後のご活躍をお祈りします。
たねまきコラム:宮津出身の私がゲノム編集魚は良くないと考えるワケ
その1.ふるさと宮津での思い出
その2.長崎(大学時代)で学んだこと、経験したこと