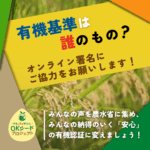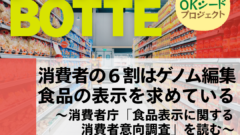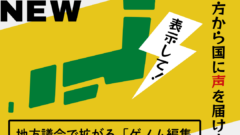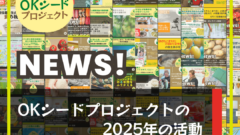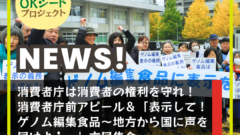はじめまして、今井昌之と申します。私は『宮津∞麦のね宙ふねっとワーク』のゲノム編集魚の公開記者会見(2025年3月8日)をオンラインで視聴して、その問題の大きさに危機感を覚えた者です。
私は、ゲノム編集魚をつくり出している(株)リージョナルフィッシュの陸上養殖拠点がある、宮津の出身者です。この記者会見で初めて知ったのですが、宮津市はふるさと納税の返礼品にリージョナルフィッシュ社によって作られたゲノム編集トラフグを送っているということです。何と! 故郷の宮津には目の前の海で獲れる新鮮な魚や美味しい干物がたくさんあるというのに! 私は大きく憤っています。ゲノム編集魚などは、まったく必要のない町です。
今回はこの紙面を通じて、私がゲノム編集魚について大いに疑問を持ち、こんな魚を人間が作り出してはいけないと思い至った経緯を理解いただくために、3回にわたってコラムを書くことといたします。
まず、この機会を与えていただいたOKシードプロジェクトの方々に感謝いたします。
1回目は私が育った宮津の町での魚とのふれあいについて、2回目は宮津を出て長崎大学水産学部で学んだ魚、水産学、漁業学や生態学のこと、そして3回目はゲノム編集魚は『良くない』と思うことについて、書きたいと思います。よろしくお付き合いお願いします。
私は1959(昭和34)年に宮津で生まれ、18歳で宮津高校を卒業するまで宮津で成長しました。その後は大学(長崎6年間)、就職して広島12年間、大阪2年、福岡26年と、転勤などで転々としてきました。現在では、日本にいることも嫌になり、昨年(2024年)8月に会社を退職して9月からはタイ国のバンコクに妻と移住して、日本から支給される年金で生活をしています。いろんな意味で日本に住んでいるのがイヤになったのです。♪思えば遠くへきたもんだあ(海援隊)♪です。
私の小学生時代の宮津
私が育ったころ(少なくとも小学生時代)の宮津は、日本がどこでもそうであったように、高度経済成長期で国全体が右肩上がりで、今のような凋落を誰も予想していなかったような時代でした(高校を卒業するころには造船不況、減量経営、200海里などで不況になる)。町の商店街は賑やかで、夏の土曜日の夕方には『土曜夜の市』が開かれ、アヒルの競走などが催され、親子連れが多く繰り出していました。衣類を売る商店はもちろん、和菓子屋さんの店先ではキンツバの実演販売(アツアツのキンツバをその場で売る)までありました。そんな夜の市の帰りには、家族でかき氷を食べて帰るのが我が家のお決まりのコースになっていました。
宮津という町は、城下町だったことから、田舎の町であったにもかかわらず、町の中で何でもそろう町でした。町の商店では、八百屋や魚屋はもちろん、江戸時代から続くお茶屋(お茶を売る店)から下駄屋、提灯屋(製造販売)までがあった町で、江戸時代は西回り廻船の寄港地として賑わい、宮津節でも♪縞の財布が空になる、丹後の宮津でピンと出した~♪と唄われるほどの遊興の地でもあり、子どものころには芸者さんのお稽古場である『検番』があったほどでした。
小学生時代は、漁師町に住む友達が多く、漁師町でよく遊んだものです。当時の漁師町では浜辺でイワシの桜干し(みりん干し)を作っていて、イワシの開きにミリンのタレをつけて胡麻を少しのせて天日乾燥させるというものでした。私たち悪童は、干物作りをしているおばさんたちの眼を盗んで、タレに指をいれてその指を舐めるのです。タレはイワシの脂も染み出して、それはそれはとても美味しいものでした。おばさんたちに見つかると、「こらーっ! どこの子やーっ!」と言って追いかけられるのです。当時の宮津では、皆、親も子どもも知り合いばかりだったので『どこの子どもや?』と叱ったのだと思います。
大手川でのイサザ獲り
川での思い出もあります。
宮津の町の中心部を流れ、宮津湾に注ぎ込む大手川(宮津城の大手門があったことから、名がついたか? ちなみに宮津城は後の熊本藩の祖である細川藤孝が築城した)での思い出です。冬は寒く雪も多く積もる(私の子どものころには毎年多くの雪が積もった)宮津ですが、5月にもなれば、暖かく水ももぬるむ時期を迎えます。
子どものころ、大手川の宮村橋付近でよく水遊びをし、そのころに、イサザ(ハゼ科のシロウオの地方名)が獲れるのです。イサザは踊食いもできる高価な魚です。私たちは被っていた野球帽で水を救いながらイサザを獲り、そのまま口に入れて『踊食い』をしたものです。宮津では5月15日が『宮津祭り』で、この時期に町にイサザ売り(木桶に生きたイサザを入れて、一合升で売る)が来たものでした。私の母はイサザを買い、祭りのごちそうに作るちらし寿司にイサザを入れたものでした。甘みのなかに少し苦みがある魚です。シロウオは長崎では3月上旬、福岡でも3月中旬から下旬が旬の時期で、今ではどこの地でも高価な魚です。
島崎海岸の磯遊び
海の岸辺の思い出もあります。
いまでは、海が埋め立てられましたが、昔は清輝楼(宮津の老舗旅館=300年の歴史があり、現在の建物は明治に建てられた木造三階建てで、高村薫の『神の火』の主人公が泊まる宿と思われる=)は海に面しておりました。その清輝楼のすぐそばに宮津高校のヨット部とボート部の艇庫があり、その地先の海岸でもよく遊んだものでした。やはりここでも野球帽が大活躍したのでした。当時の多くの小学生は野球帽を被っていたのですねえ。
その野球帽に海岸に付いている貝(イボニシやタマキビ)などを獲って貝殻を割り、中身を帽子の中に入れて、水中に入れてしばらく待っていると、魚が帽子の中に入ってくるので、それを素早く水中から引き上げて獲るのです。獲れる魚は当然、小魚でハゼ科のキヌバリだったように思います(当時は魚の種の同定技術もなく不明です)。
花火大会の宮津湾
夏にはもうひとつの思い出があります。宮津には全国的に有名な『宮津節』があります。毎年8月16日お盆の送り火の日に灯篭流しと花火大会があり、花火が終わると、皆で宮津節に合わせて宮津踊りを踊るのです。女性が踊る宮津踊りは優雅で綺麗な踊りです。
私は高校時代に友人とボート(貸しボートがFRP製に変わっていき、木製ボートを廃棄するというので、橋立の貸しボート屋から無料でもらったのです)を共有していたので、この花火を海上から見ようと、花火が打ち上げられる前に海に漕ぎだしたのです。花火の打ち上げに設置してあった海上の筏から「危ないから向こうへ行けーっ!」と怒鳴り声がしましたが、『特等席』で見るためにボートを漕いで来たのに、ここで帰るつもりはありません。
そうこうしている間に、花火が打ちあがり始めました。はじめのうちは低い高度の小規模の花火ですが、佳境に近づくにつれて大輪の、高くまで上がる花火が上がり始めます。花火がドーンッ!と鳴り響き、海上の私たちの乗ったボートの周りにジュッ、ジュッと海水に落ちて音を立てる物があります。よく見ると、花火が燃えた後の灰というか、高熱を持った残渣(火の粉に見えた)が空から降ってきて、海に落ちて音がしているのでした。これでやっと、先ほどの花火の打ち上げ筏の人達が「危ないー」と言っていた意味がわかりました。
このような海面の状況で、海中の魚が逃げまどってボートの舷に当たったり、ボートの中に飛び込んできたりします。それはもう、バチャバチャと音を立てるほど多くの魚です。花火も終わって港に戻り、ボートの中をみると魚がたくさん跳ねています。魚はサヨリ、セイゴ(スズキの幼魚)、カマス、マアジそれに産卵を終えたアユ(いわゆる落ち鮎)までが入っていました。ボートに乗っていた同級生の家が魚屋を営んでいたので、ボートに入った魚をバケツにいれて魚屋へ持って行って、買い取ってもらったものでした。
花火を打ち上げ場所の直下で見たダイナミックスさと落ちてくる火の粉の怖さとともに、海中では多くの魚が生息していることを実感したお盆の一幕でした。
好きな魚は
宮津では、魚食を中心に育ちました。四季折々、美味しい魚が食べられました。
そのなかでも印象に残っている魚は、冬に食べるオキギス(地方名=標準和名はニギス)でした。ニギスは冬のズワイガニ漁の際に底曳網に入る外道で、安い魚だったのだと思います。この魚を煮つけにしたり、干物にしたものをあぶって食べるのです。決して美味しい、高級魚ではありませんが、骨が柔らかく頭から丸ごとたべることができる魚で脂は適度にのっているのですが、少しほろ苦い味が特徴的です。
ニギスは水深100~400mの砂底に棲む魚で、深い海での底曳網を曳網すれば、日本全国どこでも獲ることができるのではないでしょうか? 高知では『オキウルメ』といって、やはり干物にしたものをあぶって、日本酒の肴として最高です。30代のころ仕事で、沖縄舟状海盆(沖縄トラフ)で資源開発調査として深海トロールの試験操業をした際にはニギスの群れに遭遇したのか、たくさん採取したことがあります。沖縄であっても深海は水温が低く、ニギスが棲息しているのです。この時は新鮮なものだったので船上で刺身にして美味しく食べました。
上等な魚はマツバガニ(宮津では雌ガニをコッペガニとして食べる=冬=)、トリガイ、アオリイカ(=夏=)、ブリ、サバ(=冬=)など、キリがありませんが、私にはニギスが印象に残っています。
もう1つだけ付け加えると、『天橋立オイルサーディン』として昔から売られている竹中罐詰(株)のオイルサーディンです。これは、文学評論家の小林英雄も宮津の清輝楼に泊まり、朝食で食べた時の感想を『世界一おいしいオイルサーディン』と絶賛(確かエッセイに書いていたと思います)しています。ふるさと宮津から遠く離れた地に住んでいた私は、鮮魚は持ち帰ることはできませんが、オイルサーディンは缶詰なので、持って帰り、美味しく食べました。
私は宮津でこんな経験をしたり、こんな美味しいもの(魚)を食べて成長したのです。
続きは、宮津から飛び出して長崎で学生時代を送ったようすを書くこととします。
たねまきコラム:宮津出身の私がゲノム編集魚は良くないと考えるワケ
その2.長崎(大学時代)で学んだこと、経験したこと
その3.ゲノム編集魚は良くない