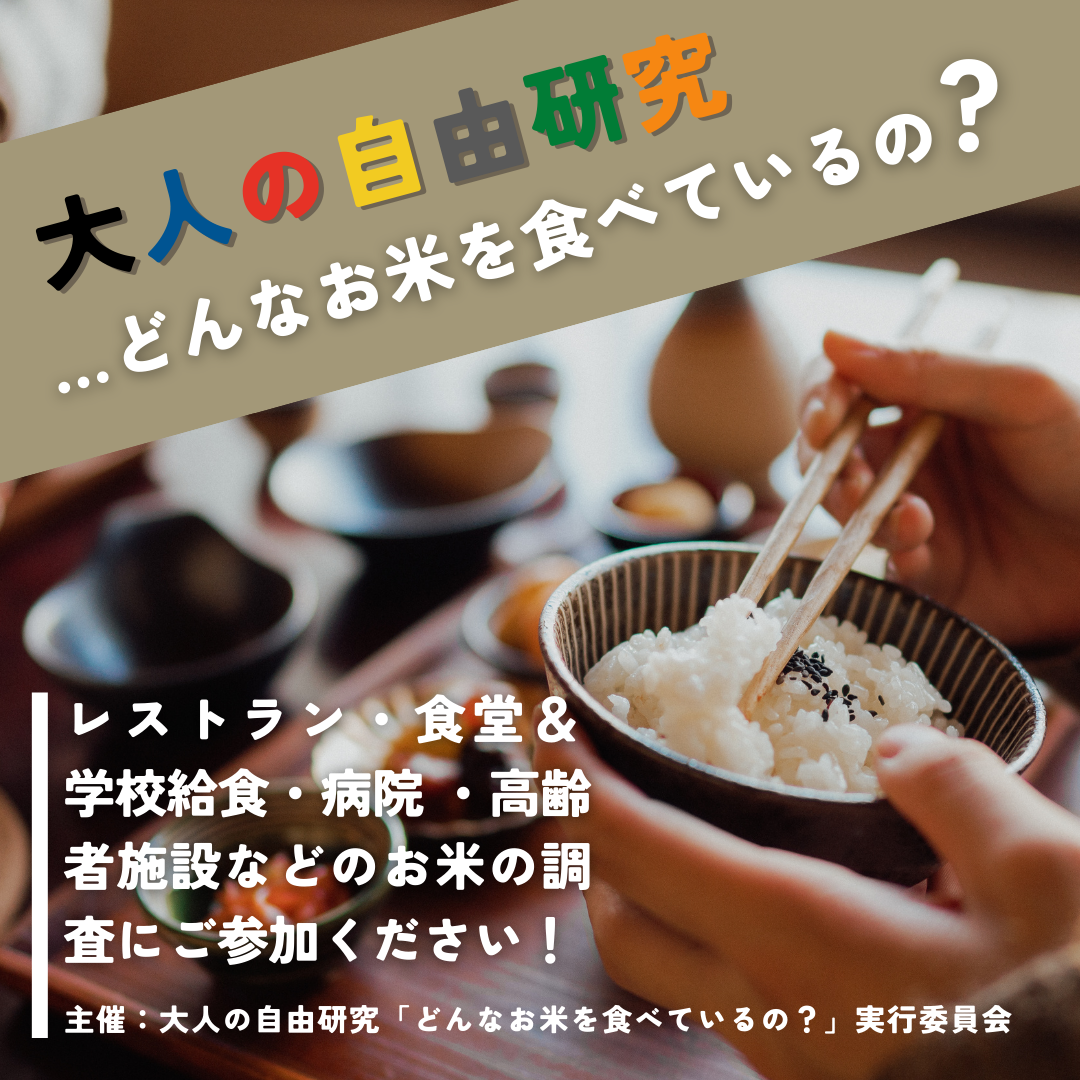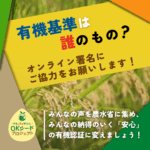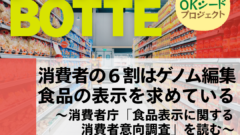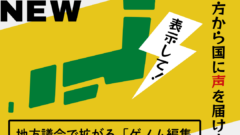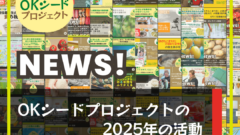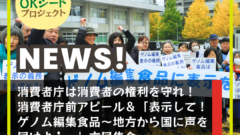米の価格高騰と米不足から見えるものは、食と農の問題だけではありません。もはや「社会問題」ともいえる危機的状況で、いま私たちがどう生きるか、どのような社会を望むのか、誰もが問われているのではないでしょうか。
そんな中、3月30日に「令和の百姓一揆」が開催されました。都心の会場ではトラクターデモを中心に、デモに参加された方、会場に入りきれずに沿道から応援された方等含み、主催者発表で4500名を超える参加があったそうです。この国の根幹を支えるのは生産者であり、彼らを守ることが、今この国が最優先すべき課題です。この日は14都道府県でも一斉にアクションが実施され、山口県では100名もの生産者と消費者が一体となって、百姓一揆のデモに集まりました。
今回、自然豊かな美しい阿東高原で有機農業を営む、阿東つばめ農園の安渓貴子・安渓遊地ご夫妻に、山口でのアクションの様子や、百姓一揆の歴史的な背景などを、貴重な資料と共に綴っていただきました!
令和の米騒動から百姓一揆へ
 私どもは縁あって2012年から息子を中心に、津和野にほど近い山口市阿東高原徳佐(1990年に水稲品種の山口1号として「はるる」が育種された山口県農試寒冷地試験場のあった場所)で、有機農業を始めました。飲める水を飲めるままで下流に流すことを目標に、化学物質を投入しない棚田を耕し、伊勢神宮のコシヒカリの神田で2度の台風被害に耐えて生き残った2株の「奇跡の稲」から選抜したイセヒカリと、酷暑にも負けずコシヒカリよりおいしい新品種「にじのきらめき」を育てています。
私どもは縁あって2012年から息子を中心に、津和野にほど近い山口市阿東高原徳佐(1990年に水稲品種の山口1号として「はるる」が育種された山口県農試寒冷地試験場のあった場所)で、有機農業を始めました。飲める水を飲めるままで下流に流すことを目標に、化学物質を投入しない棚田を耕し、伊勢神宮のコシヒカリの神田で2度の台風被害に耐えて生き残った2株の「奇跡の稲」から選抜したイセヒカリと、酷暑にも負けずコシヒカリよりおいしい新品種「にじのきらめき」を育てています。
《写真1 山口県第一号の営農ソーラーのある阿東つばめ農園(C)安渓遊地》
それにしても、日本の食べ物は、どうなってしまうのでしょう? スーパーの棚から、主食のお米がすっかり消えてしまった去年の夏。新米が出てからも品薄は続いて、1キロ1000円より安くお米が買えたら運がいいという状態です。
そんな高い米の生産農家は、さぞ儲かっているだろうと思われるかもしれませんが、農水省の発表によれば必要経費を差し引いた農業所得の平均は、2年連続で1万円、昨年は10万円弱でした。時給にして10円から97円! 1〜2ヘクタールほどの有機の家族農業をめざすわが「阿東つばめ農園」では、このところ農機具の買い替えが続いて、親の年金をつぎ込む赤字続きです。いま住んでいる集落でも、後継者がなくて農業をやめる家がほとんどという状況で、何十ヘクタールも田んぼを作ってきた法人も、事業をまるごと手放すところが出てきています。
このままでは、日本の食を支えてきた農家が日本からなくなってしまう。それは国民みんなの大問題です。それを国民にわかってもらう方法として、ヨーロッパやインドや韓国ではトラクターデモが行われていることをニュースで見ていました。
そんな中で2025年3月30日を期して、東京港区の青山公園のあたりで、トラクターデモをやろうではないか、というアイデアが浮上して、「令和の百姓一揆」と名付けられました。クラウドファンディングに2000万円もの浄財が集まりました。山口県内からも実行委員への参加があり、わたしたちも実行委員になりました。
山口県でも一揆を
トラクター輸送費の支援があるなら、東京でのトラクターデモに参加したいという声があがりました。わたしたちが毎年開いている「山口県環境保全型農業フォーラム」の席上でのことです。でも、参加可能な台数に制限があって、その願いを叶えるのは難しいとわかったので、「それなら山口でやろうじゃないか!」と思いました。
このフォーラムは、そもそも1992年に、合鴨稲作をめぐる集まりをもったのが始まりで、「山口県環境保全型農業推進研究会(山口かんぽ研)」が発足。それ以後毎年休まずに、最近は山口県内の有機農業団体の連合体である「山口県有機農業団体連絡協議会」との共催で、多彩な講師を招いての勉強会を続けてきました。全国の動き、世界の動きを、なんとか山口の食と農に関心がある人々、農家や市民に知ってほしい、と情報共有に努めてきました。種子法廃止のころからの講師は、広島県農業ジーンバンクの船越建明さん、食品と暮らしの安全基金の小若順一さん、千葉県いすみ市の有機給食の鮫田晋さん、元農林水産大臣の山田正彦さん、東京大学大学院の鈴木宣弘さん、国際ジャーナリストの堤未香さんといった方々で、今年2月23日の第34回フォーラムには、農業ジャーナリストの吉田太郎さんの基調講演で「いま子どもに食べさせるものがない!? 地域再生のカギは有機給食から」を実施しました(https://ankei.jp/yuji/?n=2929)。
おりしも山口かんぽ研では、副会長の石田卓成さんの提案で、コロナ以来減ってしまった、対面のやりとりを補うため、スマホアプリのLINEを使ってつながってみようという試みが始まっていました。フォーラムの当日には、農家だけでなく、消費者や加工・流通にかかわる仲間をはじめとする参加者のみなさんにLINEへの参加を勧めて、かなりの人数が加わってくださいました。
「百姓一揆・やまぐち」のようす
 「沖縄は東京と同時開催」という情報を紹介したりしながら、話はとんとん拍子に進みました。フォーラムがおわったその日のうちに、東京の山田正彦さんとつながり、「ぜひ山口でもやりましょう」ということになり、防府市議でもある石田卓成副会長が中心となって東京の本部とも連絡を取り合って「令和の百姓一揆・やまぐち」をやることになりました。沖縄に次いで2番目ぐらいに手をあげたのでした。
「沖縄は東京と同時開催」という情報を紹介したりしながら、話はとんとん拍子に進みました。フォーラムがおわったその日のうちに、東京の山田正彦さんとつながり、「ぜひ山口でもやりましょう」ということになり、防府市議でもある石田卓成副会長が中心となって東京の本部とも連絡を取り合って「令和の百姓一揆・やまぐち」をやることになりました。沖縄に次いで2番目ぐらいに手をあげたのでした。
山口かんぽ研に加わったばかりの方がすばやく山口用のわかりやすいちらしをつくってくれました。コースの地図もたちまちできました。
《図1 「令和の百姓一揆・やまぐち」のポスター(C)海田春海さん》
東京から、クラウドファンディングで集まった資金で作った「百姓一揆」の紺色の幟やちらし、うちわが送られてきました。それを見て、山口でもステッカーを作りました。前日の3月29日の段階での参加はトラクター3台、軽トラ14台、総参加人数38名と少ない見込みなので、土壇場での情報拡散につとめました。
心配しながら迎えた当日、集合場所の山口市にある県立山口図書館の駐車場には、ぞくぞくと人々が集まってきました。ラッパを持ったお母さん、お米の束を握った子ども、太鼓の子どもたちもいます。幟をトラクターや軽トラにつけたり、うちわやパンフレットを配ります。子どもも大人も若者も、年配のおじさんおばさんも。山口県内ですが、県境に近い岩国や下関、日本海側の長門や萩の人たちの姿も見られます。お隣の広島県の人もいます。
山口かんぽ研会長の「百姓木村」こと木村節郎さんがいそいそとステッカーを配ります。山口県や市町の議員も何人か見えます。これから出陣するという人もいます。「今朝迷ったけれど、やっぱり行こうと思って。来てよかった!」、「東京まで行くつもりだったけれど、遠いよ。山口でやれるのがありがたい!」という人。久しぶりに会えたという人、なつかしい顔、いろいろな活動のグループの 人々が集まって来られたという印象です。自己紹介をしたり、それぞれの思いを語るうちに出発の15時がやってきました。
人々が集まって来られたという印象です。自己紹介をしたり、それぞれの思いを語るうちに出発の15時がやってきました。
山口県庁前の山口市役所も近い「パークロード」をゆるゆると歩きました。トラクターを先頭に出発、軽トラが続きます。続いて徒歩隊。高々と立つ「かかし」が徒歩隊の先頭です。
《写真2 「令和の百姓一揆・やまぐち」のトラクターデモのようす(C)安渓遊地》
マイクからのメッセージは、「未来のための農政を!」「環境守る農業を!」「持続可能な農業を!」「農家の声を聞いてくれ!」「安全な食を届けよう!」「地産地消を進めよう!」「食の未来を守っていこう!」「守る、守る、みんなの食を!」「開く、開く、明るい未来を!」「山口の産物を食べよう!」「山口の農業をまもろう!」「子どもたちの未来を守ろう!」。メッセージが流れると、これに続いて、みんなでうちわを振りながら声をあげました。桜が咲く中でのおだやかな行進で、道行く人が立ち止まったり、写真をとったりしています。
トラクターは2台でしたが、軽トラが14台、歩きは警察への申請通り100人いたでしょう。こんなに山口に食や農に関心がある人がいるなんて、と感激しました。「今日は僕は勇気をいただきました。徒歩の人がたくさん来ていただいて嬉しかったです。こんなに来られるなんて。」という声。広島県からも、朝知って萩市から車を走らせてやって来た人もいました。
写真3 デモが終わって和やかに全員集合(C)石田卓成さん
ぶっつけ本番だっただけに、マイクで呼びかける「コール」の仕方や、歩き方など、打ち合わせ不足もありましたが、市民と農民が「わたしたちの食と農を守ろう」という一点でつどった、心からうれしくなるような、和やかな雰囲気のデモになりました。マスコミへの広報に力を入れ忘れたためか、マスコミは「しんぶん赤旗」と「長周新聞」(https://www.chosyu-journal.jp/shakai/34625)の2社が来ただけでした。
結果的には、東京では29台のトラクターと多数の軽トラに4500人もの参加があり、「食と農を守ること」「全ての農民に所得補償を」を柱に、行進が行われて、全国ニュースにも大きく取り上げられました。札幌市、富山市、岐阜県各務原市、浜松市、滋賀県の湖東市と近江八幡市、京丹後市、奈良市、山口市、福岡県では福岡市と大牟田市、熊本市、大分県九重町、那覇市に東京をあわせて全国計15か所で同時多発的な百姓一揆となりました。これから「食と農をめぐる連帯」を広げていくための取り組みが各地で行なわれています(https://congrant.com/project/tractormarch/14672/reports/7840)。
百姓一揆の歴史的な意味
山口県には、今回の穏やかな「百姓一揆」から思いおこされる歴史があります。それは、民衆の願いが多くの共感を集め、長州藩の政治と経済の仕組みを大きく変えて、ついには江戸時代を終わらせてしまう力となった物語です。農家では食べていけない世の中の仕組みががらりと変わる未来への希望として、天保2(1831)年の百姓一揆(長州天保大一揆)を振り返っておきましょう。
この一揆のきっかけは、借金に苦しむ長州藩が産物役所をつくって、村々の産物を専売品として安く買いたたき、大坂で高く売って収益を上げようと計画したことでした。そして、稲の不作のもとになるとして農村への持ち込みが禁止されていた犬の皮が商人の荷の中に入っていたのが、小鯖村(山口市小鯖)で見つかり、ひそかに不作を画策しているとみなされて、追跡と打ちこわしの引き金になりました。そもそも、当時の武士の俸給はお米ですから、豊作で米価が下がるより、不作で百姓が年貢に苦しもうと町民が米を買えなくて困ろうと、武士たちは米が高くなることを望むという背景がありました。
(実はその構造は現代にも引き継がれています。米不足のさなかの、2024年8月13日、大阪市の堂島取引所で米の先物取引が復活しました。https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20240820/2000086913.html 昨年の夏以降、消費者が米を買えない中でも、政府が保有米を放出しなかった主たる理由が、値上がりを当て込んだ投資家に損をさせないためだったとも思われます。2024年の農家からの買い取り価格は1俵60キロあたり1万1000円にすぎなかったのに、2025年の政府保有米落札価格は2万円以上でした。)
さて、長州天保大一揆は、またたく間に藩全体に飛び火しました。1831年7月から9月にかけて長州の全地域で10万人以上が一揆に加わりました。741軒にのぼる各村の庄屋宅と米の買い占めを行っていた店が打ちこわしに合いました。しかし、この一揆はきわめて統制のとれたもので、日ごろから憎んでいる人たちでも殺すような事はありませんでした。打ちこわしの前に、目出し頭巾をかぶった者がやってきて「これからお前の家を壊しに来るから年寄り、子供や病人があれば早く立ち退かせるがよい」と事前に伝えたといいます。そして、店の打ち壊しにあたっても、けが人や死人が出ないように、柱の芯を一寸角ほど残して鋸で切り、家がすぐには倒れないようにしてから家財道具を打ち壊しました(『南陽町誌』1964、94ページ)。
この一揆のあとで長州藩は、これまでのように百姓から搾り取るだけでは財政再建は無理であることをさとって、改革に向けて大きく動き始めます。村田清風を登用した天保の改革がスタートしたのです。若き毛利敬親藩主自身が衣食の倹約の手本となって、武士たちの俸給を半減しました。藩主専決の特別会計の撫育金を生かして「防長四白」と呼ばれた米・塩・紙・蝋などの増産に励みました(https://ankei.jp/yuji/?n=3065)。その前提として村々の産物や文化力を報告させたものが、膨大な『防長風土注進案』の貴重な記録として残されています(https://ds0n.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~bochofudo/)。
こうして培われた経済力をもとに、被差別民・百姓・町民・武士に僧侶までが力を合わせた幕末の長州藩が、薩長土肥と呼ばれた諸藩とともに、徳川幕府を倒すにいたるのは、長州天保大一揆から37年後のことでした(https://ankei.jp/yuji/?n=3051)。
自家採種と民間育種の歴史
種子法の廃止や、種苗法の改訂のような、グローバル企業の儲けを主眼にした、知的所有権を農産物にも大きく導入するという動きの中で、有機の種子を入手するのは至難の業のようになってきています。農家の収入を増やすことも大切ですが、その生産基盤の最大のものの一つが種子です。
民間育種の精華であるイセヒカリのような品種の自家採種に制限はありません。また、国の機関である農研機構が税金で開発した稲(飼料用米、ホールクロップサイレージを含む)、コムギ、オオムギ、ダイズ、サトウキビ、ソバ、ハトムギ、ゴマ、ナタネ、花き、牧草、トウモロコシ等は、とくに届け出しなくても自家採種が許諾されています(https://www.naro.go.jp/collab/breed/permission/index.html)。種子としての販売や譲渡には特別の許諾がいりますが、うちが今年から稲作の主力にしようと考えている「にじのきらめき」は、自家採種への規制をゆるくしてある例のひとつです。
そして、山口県の歴史を振り返ってみると、すぐれた稲の品種の育成には多大の努力がされてきました。いわゆる「防長米」の中で、「都」という品種は古くから有名なものです。高森(現、岩国市周東町)の農民・内海五左衛門(1805-1890)は、1851年、萩藩主のお国入りの行列のお供をして、現在の兵庫県西宮にさしかかったとき、稲掛に干された見事な稲束に目を留め、2穂を買いもとめました。玖珂(くが)の親戚の田中重吉とともに改良を重ねて良質米に育て「都稲」と名付けました。都稲は大坂市場でも好評で、藩主の御膳米にも用いられ、防長米の主力となりました(http://heisei-shokasonjuku.jp/kids/utsumigozaemon/)。
天保大一揆の発火点になった小鯖村の篤農家・伊藤音吉(1856-1912)は、1889(明治22)年に都稲から早生の品種を育成し、「穀良都(こくりょうみやこ)」と名付けました。この品種が、1999年になって山口県で復活しました。これを母方とし、山田錦を父にもつ「西海222号」を父方として交配・選抜して「西都の雫(さいとのしずく)」という酒米の品種がつくられて、各日本酒メーカー が良酒を競作するということが、現在行われています(http://y-shuzo.com/products/saitonoshizuku.html)。
が良酒を競作するということが、現在行われています(http://y-shuzo.com/products/saitonoshizuku.html)。
この国の農と食を子どもたちにも安心して手渡せる喜ばしい近未来のために、みなさんとともに美酒で乾杯したいものです。
写真4 「西都の雫」を使って競作された山口県のお酒(C)山口県酒造組合・山口県酒造協同組合
※参考:著者 安渓遊地さんのブログ https://ankei.jp