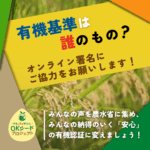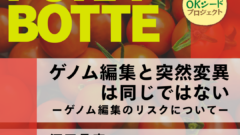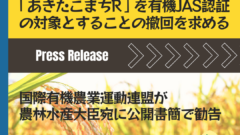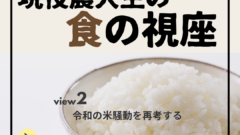谷口吉光(あきたこまちを守る会世話人/秋田県立大学名誉教授)
2025年6月28日、秋田市で開催された「あきたこまちを食べ続けたい、作り続けたい」人のための6・28県民集会には、オンライン参加を含めて約120名の市民が参加しました。会場では用意した椅子席が一杯になり、参加者は基調講演とパネルディスカッションの内容に熱心に聞き入っていました。
集会を主催したのは「あきたこまちを守る会」という市民団体です。「これまでのあきたこまちを作り続けたい、食べ続けたいと願う生産者と消費者の選択権を守るための活動を行う」ことを目的に掲げ、2025年4月10日に設立されました。田口則芳代表世話人をはじめ、10名の世話人によって運営されています。私も世話人の1人です。
集会の最初に、私が「あきたこまちR全面切替 7つの疑問」と題した基調講演を行いました。ご存じかもしれませんが、秋田県はこの春からこれまでの「あきたこまち」の種もみの供給を取りやめ、重イオンビームを使って放射線育種した「あきたこまちR」(こまちR)に全面切り替えしました。読者のみなさんは、今、秋田県の水田で育っているのは去年までと同じ「あきたこまち」だと思っているかもしれませんが、実際には98%が「こまちR」に置き換わっています。ですから、この秋から出荷される秋田県産あきたこまちの新米は、ほぼすべて「こまちR」になるのです。
私は「こまちR全面切り替え」は非常に問題が多い政策だと思っていて、このことを知った2023年8月からずっと反対を訴えています。すでに講演や雑誌記事などで反対意見を述べてきましたが、この集会では「こまちRはこれまでのあきたこまちと同等だ。だから安全だ」という秋田県の主張に対して、具体的な事実に基づいて疑問を提示しました。講演の概要をご紹介します。
こまちR7つの疑問
疑問1 こまちRが安全かどうかは食べる人が決めることではないか?
秋田県は「放射線育種されたこまちRに放射線が残っていることはなく、自ら放射線を出すものでもありません。だから安全です」と主張しています。しかし、問題は米に放射能が残っているかどうかではなく、重イオンビームによってイネの遺伝子が壊されたことです。ある人にとって安全でも、別の人にとっては危険だという食べものはたくさんあります。病気やアトピーなどを抱えて、1人ひとりの市民が“自分の安全の基準”を持っているのです。それなのに、秋田県が一方的に「こまちRは安全だ」と押しつけるのは間違っていると思います。
疑問2 こまちRとあきたこまちの食味は同じなのか。
秋田県は、米の流通業者を対象に「こまちR食味アンケート」を行い、その結果をもとに「こまちRの食味はあきたこまちと同等だ」と主張しています。私はそのアンケート結果を入手して、再分析しました。その結果「甘味、粘り、硬さの点で、こまちRの食味が劣るという意見が多かった」ことを突き止めました。特に、あきたこまちの食味で重要な「粘り」については、「やや悪い」「悪い」の合計が27.4%と4分の1を超えていました。これで食味が同等といえるのでしょうか。
疑問3 こまちRとあきたこまちの生育特性と栽培方法は同じなのか。
「こまちR」の生育特性と栽培方法を農家向けに説明する「こまちR栽培暦」という資料があります。これを農家と一緒に分析した結果、こまちRは収量が15㎏/10a低く、「千粒重」などの数値があきたこまちより低いことがわかりました。こまちRはカドミウムだけでなく、マンガンも吸収しないため「ごま葉枯れ病」にかかりやすく、高温に弱いともいわれています。栽培歴では、マンガン肥料を増やすことやごま葉枯れ病を防ぐための追加防除(農薬散布)が求められています。つまり、農家には減収リスクがあり、肥料代や農薬代の追加支出、手間が余計にかかるのです。全面切り替えによって農家はこれまでのあきたこまちを選ぶことができないため、こうした不利益を受け入れざるを得ません。
疑問4 減収になった場合、なぜ県は農家に減収補償をしないのか?
あきたこまちを守る会では、秋田県に「あきたこまちRを作付けして減収になった農家には減収分を補償してください」との要望書を提出しました。しかし県からは、「こまちRとあきたこまちの収量・品質は同等であることが示されており減収に対する補償は考えておりません」との「ゼロ回答」が届きました。
これまで、新しい米の品種を導入する時は、農家の反応を見ながら、少しずつ面積を増やしてきました。農家が実際に育ててみて、納得できた品種だけが広がってきたのです。しかし、こまちRの場合、農家は一度も栽培したことのないこまちRを作付けさせられています。しかも、未知の減収リスクがあり、費用や手間が掛かり増しになることが確実です。なのに、費用の補助もなければ、減収しても補償がないというのです。そんな理屈が通るのでしょうか。こまちR全面切り替えは、農家の権利や尊厳を踏みにじる暴挙だと思います。
疑問5 なぜ、「あきたこまちR」と正直に表示しないのか
秋田県は「あきたこまちとこまちRは同等だから、こまちRをあきたこまちと表示して販売しても問題はない」といっています。こまちRの安全性に疑問を感じている消費者・市民が、これまでのあきたこまちを選べなくなる(=消費者の選択の権利が奪われる)ことが、まったく考慮されていません。
しかも、不思議なことに、生産段階では「こまちR」という言葉が堂々と使われていて、ホームページでは「米産県である秋田県としては、どこよりも早くカドミウム低吸収性品種を導入して、従来の『あきたこまち』から『あきたこまちR』に切り替えることで、国内外の消費者に、これまで以上に安全な米を安定的に供給し、食糧供給基地としての使命をしっかり果たしてまいります」と自信たっぷりに書かれているのです。そんなに自信があるなら、堂々と「こまちR」と表示すればいいのではないでしょうか。なぜ、このような「二枚舌」を使うのでしょうか。
疑問6 なぜ、こまちRでも、有機JAS認証が認められるのか?
農水省は「こまちRでも有機JAS認証を取得できる」と決定しました。有機農業推進法では、有機農業とは「化学肥料、化学合成農薬、遺伝子組み換え技術を使用しない農業」と定義していますが、「放射線育種は遺伝子組み換えではないから、有機農業と認めてもよい」と判断したものです。しかし、これは全国の有機農家や消費者団体に説明も相談もなく決められました。秋田県有機農業推進協議会は「こまちRを有機農業とは認めない」という声明を出しています。農家や消費者の要望を無視した農水省の決定は大問題です。
疑問7 なぜ、希望する農家にあきたこまちの種を供給しないのか?
あきたこまちを守る会は、秋田県に対して「あきたこまちの種子を希望するすべての市町村と生産者に提供してください」との要望を提出しましたが、長い理由をつけて技術的にできないという回答の後に、「あきたこまちの種子が必要な場合は自家採種するか、他県から購入いただくことになります」とまったく突き放した返事が届きました。
これに対して、あきたこまちを作り続けたい農家からは次の反論が寄せられています。「自家採種すれば近親交配になって品質・収量が低下する」「他県で育成された『あきたこまち』の種子は他県の天候などの影響を受けて性質が違ってくる」「これまでの『あきたこまち』を食べ続けたい消費者のために、秋田県は責任をもって種子を供給すべきだ」。
あきたこまちを守るためにできることは?
基調講演に続いて、秋田県内の生産者と消費者4人による「あきたこまちを守るためにできること」と題したパネルディスカッションが行われました。重要な意見としては「生産者も消費者もこの問題を知らない。知らされていない」「県外のデパートや卸業者からは『あきたこまちを買いたい。こまちRなら買わない』という意見が多い」「問題は来年度の種もみをどう確保するかだ」「あきたこまちを食べたい消費者と、作りたい生産者をどうつなぐか」「この問題を知ってもらうことが大事」などが出ました。その後、会場との意見交換があり、たくさんの意見が出されました。全体として、集会は大成功だったと思います。
なお、集会の動画データはまもなくYouTubeで一般公開される予定です。
こまちRの問題は生産者と消費者の権利の問題
2025年7月8日、あきたこまちを守る会の世話人会が開かれ、集会の振り返りを行いました。新聞報道としては、秋田魁新報が大きな写真を含めて集会のようすを経済面トップで報じてくれました。守る会が設立されてから、メディアの扱いが大きく変わったと感じています。5月7日に守る会が秋田県農林水産部長に会って要望書を提出した際には、秋田魁新報のほか、県北部をエリアとする北鹿新聞が2面トップ、宮城県をエリアとする河北新報が報じてくれました。テレビでは、ABS秋田放送が夕方のニュース番組で5分ほどの特集を組んでくれましたが、守る会の主張も報道してくれ、この特集は今でもYouTubeで一般公開されています。
これまでメディアは「こまちRは安全だ」という県の主張を一方的に報じるだけでしたが、守る会ができてからは賛否両論を取り上げてくれるようになりました。こうした変化は、守る会が立ち上がり、「こまちRの問題は生産者と消費者の権利の問題」だという会の主張に一定の根拠と社会的意義があることをメディア各社が認めたことの表れだろうと考えています。
集会のもうひとつの成果は、新たに46人が守る会の賛同人になってくれたことです。守る会は、会員方式を取らず、会費も集めないという運営方針を立てています。それは毎年総会を開いたり、会費を集めて管理するという煩雑な事務作業を省略するためです。会員の代わりに「賛同人」、会費の代わりに「カンパや寄付」をもとに運営することにしているのです。11人の世話人と合わせて、50名を超える仲間を得て、団体の基盤を固めることができました。引き続き、県内外問わず賛同者を募集しています。守る会の田口代表まで、住所、氏名とメールアドレスをご連絡下さい(hyakusyoutaguti1234@gmail.com [迷惑メール対策のため@は全角になっていますので、メール送信の場合は半角@に変えてください])。
今後の課題としては、今年度(2025/令和7年度)産の米はほぼこまちRに変わってしまったわけですが、来年度(2026/令和8年度)にあきたこまちの作付けをどのくらい増やせるかが重要です。そのために、県内外の消費者個人や団体からの注文の取りまとめ、生産者とのマッチング、あきたこまちの種もみの確保、乾燥調整施設の確保などの具体的課題の解決が求められます。
守る会では、県内外の賛同者・支援者の方々と連携して、生産者と消費者の選択権を守るための運動を続けていきます。引き続きご支援をよろしくお願いいたします。