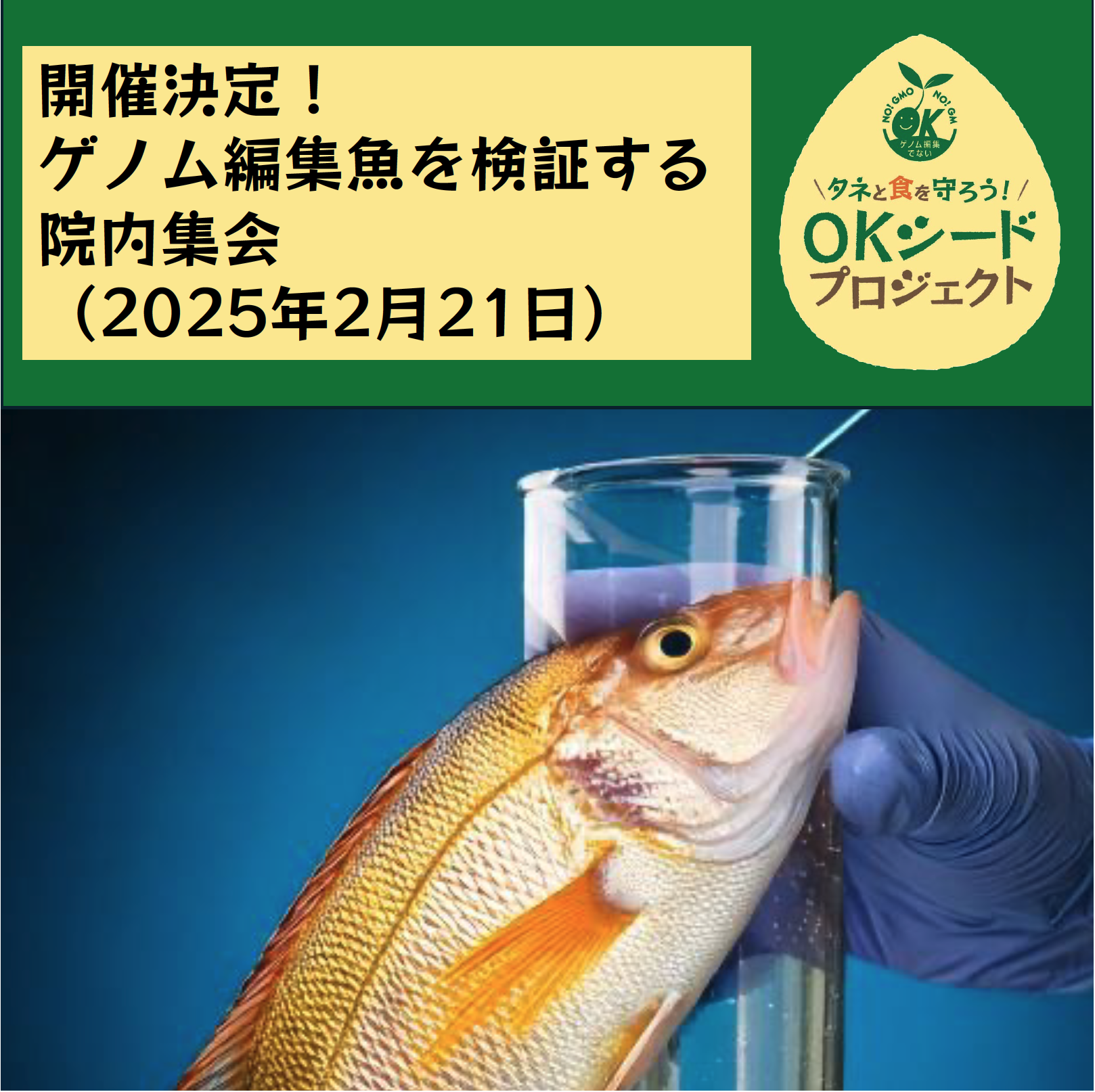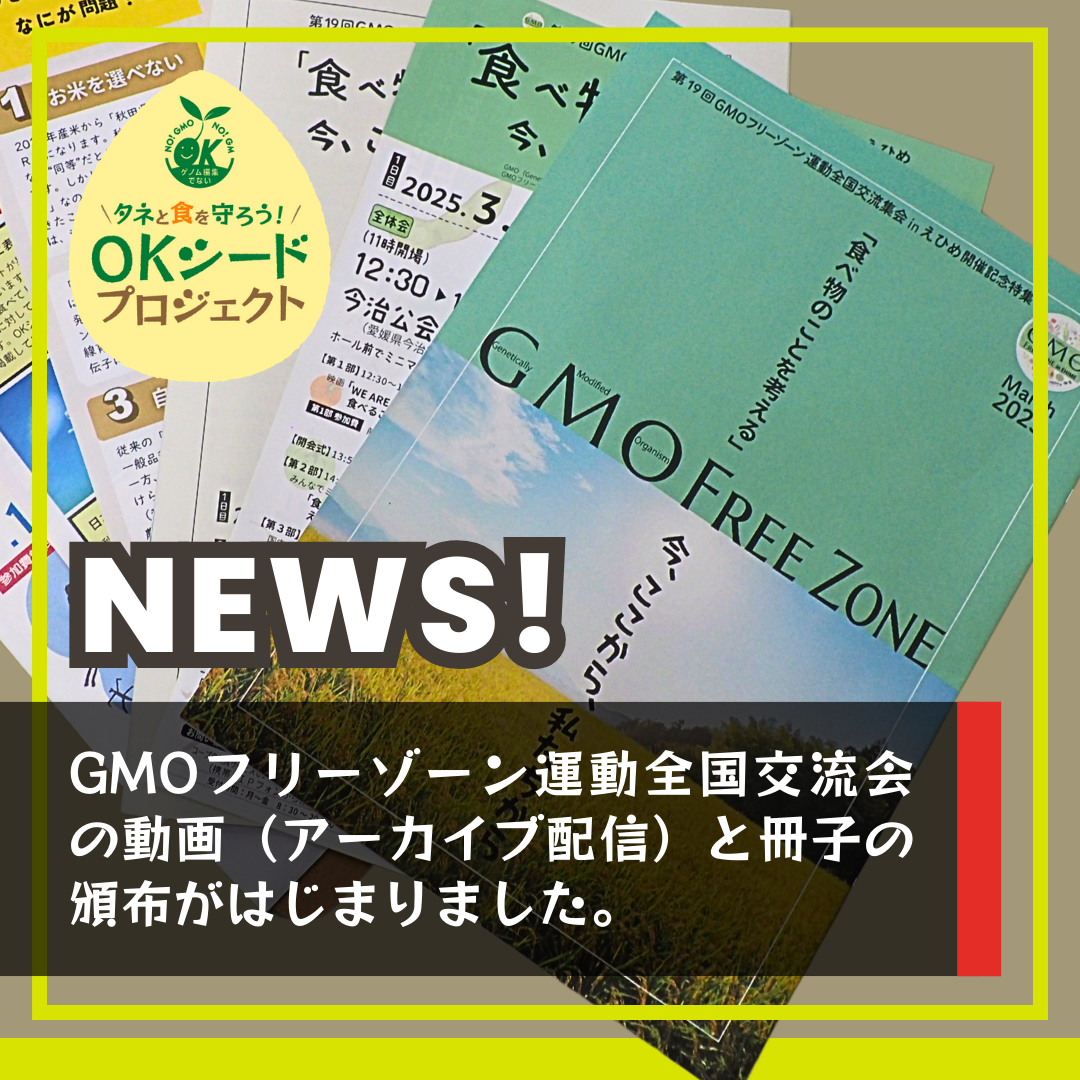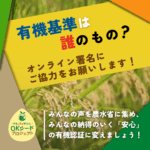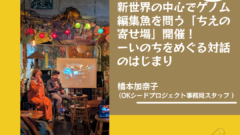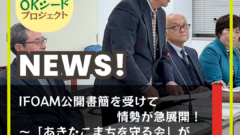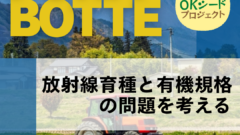3月24日のオンライン学習会「米騒動とバイオテクノロジー」の動画を公開しました!
講座は1時間程度、その後の質疑も20分程ですので、ぜひ家事をしながら、通勤や移動の合間などに観ていただきたいです。
《オンライン学習会:米騒動とバイオテクノロジー》
https://youtu.be/sluxDEN0li8
https://youtu.be/sluxDEN0li8
今回の講座では、事務局長の印鑰智哉から、とても重要な問題提起が共有されました。
食と農の大きな分岐点にいる「今」を、みなさんと一緒にしっかりと見つめ、これからのことを考えていきたいと思います。
食と農の大きな分岐点にいる「今」を、みなさんと一緒にしっかりと見つめ、これからのことを考えていきたいと思います。
以下、事務局長の印鑰智哉のFacebookの投稿から引用します。
———-
なぜ、米不足なのにそれに農水省はまともに取り組もうとしないのか、食料自給率が日本だけ下り続けているのに、農水省はそれを上げるよりも、未だに輸出を増やすということばかり熱心に進めているけれども、それはなぜ?
なんで、ここまでの危機的状況になっているのにまっとうな対応が出てこないのか、どう対処していったらいいか、今の日本で、もっとも喫緊な課題の一つになっていると思います。
農業・食料の政策がどう歪められているか、それを見ていくと、日本でも巨大企業と政府の回転ドアが完成していることがわかると思います。結局、市民・農民そっちのけで政策が続けられてきたそのツケが今、出ていると言えると思います。
この責任をはっきりさせていかないと、大変なことになる、というのも、政府が責任を認めずに、問題は流通にある、とか言えば、流通で誰かが米価をつり上げている、としていもしない犯人捜しが始まるでしょう。犯人にされてしまえば、どんな暴力が加えられるかわかりません。そして、そんな間違った騒ぎを起こしても、肝心なお米は確保できません。
お米を作る生産者を守る政策を一刻も早く実現させて、政府がそれに踏み出すことを求めるしかありません。そこにエネルギーを集中しなければならないはずです。
この問題について24日、オンライン学習会で問題提起させていただきました。
なぜ、食料自給よりも貿易の最大化を優先するのか、地域の食の担い手がどんどんいなくなってもまったく問題としようとしないのです。地域の食のシステムの中の中心は小規模生産者であり、地域企業ですが、それらが元気だと、大きな企業が儲けることはできない。でも彼らを追い出せば、ボロ儲けができることになるのです。そして、その勢力が同時にフードテックを進める勢力でもあります。
だからこそ、規模や農法には関わらず、地域のすべての生産者を守る。そして地域の食品企業も現在、大変な状況になっています。そうした人たち含めて、地域の食のシステムを守ってこそ、本当の食の安全を守ることができます。
3月30日は日本全国で百姓一揆、日本全国で農家を守るための行動が取り組まれます。まずはその生産者の保護を実現するために、力を合わせましょう。