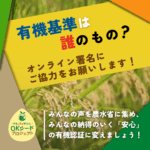遺伝子組み換えの実験が開始されてから、今年で半世紀。今、遺伝子操作の範囲はさらに広がっています。新しいゲノム編集技術というものによって、どのように種子開発が進められているか、そして遺伝子操作技術の基本的な知識や歴史的な流れについて、天笠啓祐さんに詳しく教えていただきました。
後半の技術的な内容は、非常に専門的かつ複雑で、私のような一消費者にとっては理解に至ることがとても難しい内容でした。だけど少しでも理解したいと、頭がよじれるような感覚で、必死に説明に食らいついて聴きました。
天笠さんのお話しから、遺伝子操作の基本は50年前の遺伝子組み換えの始まりから実は変わっておらず、そして現在まで「いかにして規制を逃れるか」という点で新技術が開発されてきたということがよく分かりました。人間の傲りを大変な脅威に感じ愕然とし、また、こうして遺伝子などミクロの世界に目を凝らしながら、生命について考えたときに、自然界にある生きものは既にそれぞれ完成の域に達しているのであり、そしてどの生命もなにものにも変えられない尊いものであることを感じています。
人間が手を加えてよい遺伝子などないと、改めて私の中に揺るぎない答えを刻むことができました。
天笠さん、貴重な講義をありがとうございました!
今回、天笠さんのご厚意で学習会の録画を期間限定で公開しましたので、しっかり復習して理解を深めていきたいと思います。
◆動画はコチラから
まだまだ理解には遠く及ばず理解できた限りではありますが、OKシードプロジェクト事務局の橋本がレポートをまとめました。
ぜひ御覧ください。
===========================
《遺伝子組み換えの規制の歴史》
◆遺伝子組み換えが全ての「出発点」
1973年、ハーバート・ボイヤー(カルフォルニア大サンフランシスコ校)とスタンレー・コーエン(スタンフォード大学)が、遺伝子組み換え実験の方法を確立。当時使用していた方法は、大腸菌とプラスミドを用いた実験だった。
その翌年の1974年、スタンフォード大学のポール・バーグが「これはたいへん危険な実験だ」として、「バーグ声明」を発表し、これによって遺伝子組み換え実験が一時停止される。科学者が初めて自主的に実験を中止し、世界的に話題になった。
1975年には実験再開を目的として、米国カリフォルニア州で国際会議「アシロマ会議」が開催される。遺伝子組み換え実験を、規制した上で再開することが、科学者だけで決められた。
1976年にはアメリカの国立衛生研究所(NIH)が実験指針を作成し、日本でも1979年に実験指針が作られた。
◆2つの封じ込めによる「規制」
①物理的封じ込め
遺伝子を組み換えた生物を実験室の外に出さないよう求めるもので、P1~P4という4段階で、この規制の枠組が決められた。
・P1:理科の実験室程度のような、室内を陰圧にする程度の簡単な規制。陰圧とは、外よりも中(実験室)の空気圧を下げることで、例えばガラスにヒビが入るような事態になっても外から中に空気が入るため、室内の微生物などが外に出ないというもの。
・P4:グローブボックス使用など厳しい規制。例えば原子力でいうと、プルトニウムを扱うような厳しい規制のある部屋のことを指す。現在、日本でP4の施設があるのは、筑波研究学園都市にある理科学研究所の研究施設と、武蔵村山市にある国立感染症研究所の研究室の2箇所のみ。
②生物学的封じ込め
万が一環境中に漏れ出たとしても、そこでは生きられないような生物を用いることを求めるもの。例えば抗生物質がないと生きられないなど、環境中にない成分を必須とする生物など。
(例:遺伝子組み換えの「蚊」の放出実験では、環境中に放出するけれども、それが長生きできないような形にして放出する)
しかし、生物は何が起きるかわからず、生き延びてしまう可能性もあるため、「とりあえずの規制」でしかないものである。
◆カタルヘナ国内法
日本の法律に「カルタヘナ国内法」という後述する生物多様性条約のカルタヘナ議定書の国内法があり、大学やいろいろな企業の研究室で行う実験に対しても適用されている実験指針という原則がこの法律の下に作られている。ここで上記の「物理的封じ込め」や「生物学的封じ込め」というものが活きている。
しかし、その後、実用化の段階を迎えることで、実験指針の意味合いが異なってしまう。
◆実用化の時代
1980年代に遺伝子組み換え作物の開発が進み、野外で栽培することが前提となり、「封じ込め」の原則は役に立たず、新たな規制が必要となる。
1992年6月、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された国連環境開発会議(地球サミット)で生物多様性条約の署名が始まる。この生物多様性条約の中に、バイオセーフティー議定書づくりが盛り込まれ、遺伝子組換え生物などの規制を求める議定書となる。
このバイオセーフティ議定書は、通称「カルタヘナ議定書」と呼ばれる。先の「カルタヘナ法」は、この国内法。
◆カルタヘナ議定書のポイント
カルタヘナ議定書では、前文で予防原則を求めており、国際条約のため、遺伝子組み換え作物などの国際間移動を規制している。
第8条では、輸出国に情報の正確さを確保するため、輸入国にも国内規制を求めている(法律でなくてもよい)。そのため、日本でもカルタヘナ国内法が作られた。
※日本は輸出国:日本は、作物の視点で見ると「輸入国」だが、実はいろいろな遺伝子組み換え生物やバイオテクノロジーで改造した生物なり微生物をたくさん輸出しており、その意味では「輸出国」でもある。
第27条では、損害(生物多様性への影響)が生じてしまったような場合に、その修復の方法を4年以内に確立するよう求めた。これが2010年に「名古屋・クアラルンプール補足議定書」として合意されることになる。
2000年1月に生物多様性条約・特別締約国会議がカナダのモントリオールで開催され、そこでカルタヘナ議定書が採択され、2003年6月に同議定書が発効される。しかし、その時すでに、モンサントが何年も前から遺伝子組み換えのトウモロコシや大豆などの栽培を世界中で進め始めていた。
◆規制の流れ
規制は生物多様性影響評価以外に、食品の「安全審査」や「食品表示」等があるが、これは国際条約に定められておらず、各国の判断になる。そのため、厳密なものでなく、日本は特にひどかった。
食品の安全性審査の基本は、実質的同等性に基づくことになり、例えば遺伝子組み換え大豆も通常の大豆も、同じ大豆であれば実質的に同等とされ=異なった部分だけ評価される。これによりきわめて緩い規制となり、食品表示もタンパク質が残ってるか否かで表示するかしないかを決めた。同じ遺伝子組み換え大豆を原料としていても、タンパク質が残っている味噌は表示するが、タンパク質が残っていない醤油は表示しなくてよい。
◆ヨーロッパの厳密な表示制度
EUが厳密な食品表示制度を作った。これは日本のようにタンパク質が残っているか否かではなく、全食品表示であり、しかも全成分表示である。混入率も0.9%以下とした。日本は5%以下なので、その違いは大きい。その結果、 ヨーロッパでは遺伝子組み換え作物が流通できなくなり、開発も滞った。これが1つの大きなポイントとなる。
◆日本のカルタヘナ国内法
2004年2月19日に日本で「カルタヘナ国内法」が施行される。これは第1種使用と第2種使用の2種類に分かれている。
①第1種使用:野外での解放系の使用。生物多様性評価を行い承認を得ること。
②第2種使用:施設内の使用で、環境への拡散防止措置を取ることであり、これは物理的封じ込め/生物学的封じ込めに準じるものであった。
また、遺伝子組み換え作物などの輸出者は、相手国に通告(内容等を表示)したもの以外は輸出できず、遺伝子組み換えしたものであるということを、きちんと通告しなくてはならないということを示している。
◆カルタヘナ国内法の問題点
カルタヘナ議定書は予防原則を打ち出してるにも関わらず、国内法では予防原則は輸入規制になる可能性ありとして制限した。すなわち、「予防原則を採らない」とした。「人の健康」への影響については、「考慮」という言葉で外し、「食品の安全性」は対象外とした。
そして生物多様性評価の対象から農作物を排除した。例えば遺伝子組み換えナタネがブロッコリーや大根との交雑が起きてることを「遺伝子組換え食品を考える中部の会」が見つけ出したが、農作物は対象外であるため、交雑が起きても問題ないとされ、いわゆる規制の対象にはならない。
また、昆虫や鳥など動物への評価も限定し、事実上しなくてもよいということになった。
◆隔離距離
農水省がこのカルタヘナ国内法を施行した時、隔離距離の指針をつくった。これは遺伝子組み換えの作物を栽培した時に周囲とのその農作物の間にどのぐらい距離を持たなければいけないかというものである。
例えば、イネは30m以上、大豆が10m以上、トウモロコシは600m以上、ナタネは600m以上、隔離距離が必要としている。ところが、これは花粉が飛んでしまえば交雑が起きてしまうような距離である。
北海道では遺伝子組み換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例が独自に作られ、その隔離距離は、イネは300m以上、大豆は20m以上、トウモロコシは1200m以上、ナタネは1200m以上、てんさいは2000m以上となった。この距離でも交雑が防げるような距離ではないものの、しかし農水省の指針に比べると倍(イネの場合は10倍)の隔離距離を取っている。通常、農水省の方針を超えた条例というものは作りにくいが、北海道はそれを作ったというところに意義がある。ただし、これは試験栽培のための隔離距離であり、一般栽培はこれに準じるという形になっている。
◆どのぐらい花粉が飛ぶか
故・生井兵治教授(元筑波大学教授)が、「花粉の寿命×風速」で交雑の可能性の範囲があることを指摘されている。イネの場合、花粉の寿命が5~6分で風速が5mの時、交雑の範囲は1.5kmになる(例えば、風速1mであればこの1/5になる)。トマトの花粉の寿命は3~4日のため、風速5mで単純計算すると、交雑の範囲は1296kmとなる。小麦やキャベツなど花粉の寿命が非常に長いものもあり、隔離距離というのは大変重要な意味を持ってくる。
しかし、そもそも隔離距離を取ったとしても、なかなか交雑を防ぎきれるものではないということを生井先生は指摘されていた。
ここまでの規制の大きな流れを振り返ると、国が遺伝子組み換え作物の規制を、いかにしたくなかったかということがよく見えてくる。そして、欧州で、この規制逃れのための技術開発が進んでいくことになり、これが「新育種技術」と言われるものである。
《規制逃れの技術開発》
◆ヨーロッパで進んだ「規制逃れ」の技術開
ヨーロッパでは食品表示制度によって遺伝子組み換え食品の流出を事実上阻止したため、研究者あるいは企業は、このままでは開発が遅れるという危機感を持った。そこで「遺伝子組み換えではない」という規制逃れのための遺伝子操作技術の開発が進められた。それが今、「新育種技術(NPBT、New Plant Breeding Techniques)」といわれるものである。
開発の中心はオランダの研究者で、欧州委員会(EUの政府機関)はNPBT(現在のいわゆる規制逃れの遺伝子操作技術、新育種技術)を規制しないように働きかけを始める。 欧州委員会のJRC(Joint Research Center/規制しない専門委員会)が、規制しないことを前提に2011年にNPBTを定義した。
◆NPBTで取り上げた8種類の技術
①ゲノム編集(ZFN) ②オリゴヌクレオチド指定突然変異導入技術(ODM) ③RNA依存DNAメチル化(RdDM) ④シスジェネシスとイントラジェネシス ⑤接ぎ木 ⑥逆育種 ⑦アグロインフィルトレーション ⑧人工ゲノム
基本的にこの8つの技術は、「外来遺伝子が残っていない」ということがポイントである。ゲノム編集技術が登場してきた時、日本でも「遺伝子組み換えではない」ということを政府が盛んに強調した。その時の最大の言い分が「外来遺伝子が残っていない」「切断するだけ」という論理だった。その論理を最初に作り上げたのはヨーロッパの研究者たちだった。
日本でも日本会議が2014年にこの新育種技術を取り上げ、「植物における新育種技術(NPBT)の現状と課題」を作成した。ここで欧州委員会がまとめた8種類に加えて、 「SPT(Seed Production Technology)」という種子生産の技術を加えたため、9種類となった。(人工ゲノムがうまくいかないため、結局8種類)
◆CRISPR-Cas9の登場
日本を含めて世界各国がこのヨーロッパの動きを見習い始め、このNPBT(新植物育種技術)というものは、さらにCRISPR-Cas9の登場によって大きく変わっていく。
2010年前後にこの動きが始まり、外来遺伝子が残っていないということを前提として、ゲノム編集技術の規制を行わない動きを強めた。新しくCRISPR-Cas9が登場し、ヨーロッパのこの考え方が活きてしまう。ヨーロッパの欧州委員会がNPBTとCRISPR-Cas9を規制しないという方針を打ち出し、ここから一気にNPBTがクローズアップされることになる。それにより、「規制をさせまい」とする動きが活発になった。
これに対し、市民団体が欧州司法裁判者に訴えた。2018年4月25日に欧州司法裁判所の判決が下され、市民団体が勝訴した。欧州委員会の「規制しない」という方針は無効となる。
◆エピゲノム編集技術の登場
ヨーロッパは「規制させまい」という動きをとっており、CRISPR-Cas9というゲノム編集技術が登場したことによって、さらに、「エピノム編集技術」が登場する。
NPBTはNGTs(新ゲノム技術)という言い方に変わり、 欧州委員会は2023年7月5日、このNGTs(新ゲノム技術)の規制の全面緩和を提案。環境保護団体など市⺠は、従来通り規制すべきであると主張している。
前段階であるRNA依存DNAメチル化技術とゲノム編集技術がちょうどと繋がったようなものが、「エピゲノム編集」であり、ゲノム編集技術が登場しなければこのエピゲノム編集技術は登場しなかったといえる。
◆新しい種子開発の方法
前述のとおり、新しい種子開発の方法は8種類ある。
1.ゲノム編集
最初にヨーロッパの研究者なり企業が規制させまいとして取り上げたのが、 第一世代「ジングフィンガー法」(ZFN)。その後、2010年に第二世代のターレン(TALEN)という方法が出て、第三世代のCRISPR-Cas9が登場した。CRISPR-CasにはCas9以外にもいろいろあるが、やはりCas9の登場は決定的であり、これに勝るものはなかなか出てこない。
CRISPR-Cas9はガイドRNAとDNA切断酵素の組み合わせということになる。これがゲノム編集技術。
重要なのは、CRISPR-Cas9というのは遺伝子組み換えと全く同じ方法を使っているということ。遺伝子組み換えとゲノム編集というのは、たとえば、新しく除草剤耐性遺伝子が加わるか、DNAを切断するCas9が切断するかの違いだけであり、そういう意味では、新たなDNAが残っているか否かが、規制するかしないかのポイントになった。
2.オリゴヌクレオチド指定突然変異導入技術(ODM)
標的とする遺伝子を、導入する遺伝子と入れ替える方法。入れ替えるというのは全く同じものではないが、本当に短い遺伝子を少し変化を持たせると、遺伝子に突然変異が起きる。これは「ほとんど類似した遺伝子を入れ替えるため、遺伝子組み換えではない」「新しく遺伝子を入れるわけではなく、入れ替えるだけなので問題ない」という考え方になる。
3.RNA依存DNAメチル化(RdDM)
RNAを用いてDNAの修飾を操作する技術で、DNAに直接働きかけるのではなく、付随した修飾部分に働きかけるもの。このDNAのメチル化という考え方がエピゲノムの問題に発展し、これとゲノム編集が組み合わさったものが、エピゲノム編集という形になってくる。
4.シスジェネシス
遺伝子組み換えを行うが、同じ種か近縁種しか使わないものをシスジェネシスという。例えばトマトの遺伝子組み換えを行う場合、トマトの遺伝子か、トマトの近縁種の遺伝子しか使わない。
安全性評価の指針「実質的同等」の観点から、トマトと遺伝子組み換えトマトは同じトマトだという論理になる。トマトの遺伝子しか使ってないのだから遺伝子組み換えとは言えないということ。他の種の生物を使っているわけではないから、問題ないという考え方。
5.イントラジェネシス
遺伝子組み換えで同じ種か近縁種の遺伝子を導入する。シスジェネシスとの違いは、同じ種のあるいはこの近縁種の遺伝子を導入するが、プロモーターやターミネーターといった脇役に他の生物種を使うケース。
プロモーター:組み換えた遺伝子の働きを起動させる役割
ターミネーター:組み換えた遺伝子の働きを終了させる役割。
6.接ぎ木
• 台木は遺伝子組み換えだが、接ぎ木の実がなる部分は非組み換えの樹木
• 台木の性質が接ぎ木で実る果樹にもたらされる
例えば、リンゴ台木の遺伝子組み換えの性質が、非遺伝子組み換えの接ぎ木に実ったりんごの実にもたらされるという考え方。実際に日本でも青森あたりで研究されているという。
7.逆育種
優良な品種ができた時に、それを優良系統としてさかのぼって確立し固定化する方法で、RNA干渉法を用いて余計な遺伝子が働かないようにする。
RNA干渉法の場合は遺伝子を加えず遺伝子の働きを抑える方法のため、新しい遺伝子を使っていないことが強調される。
8.アグロインフィルトレーション
病気にかかわる遺伝子を導入した微生物を作物の葉に感染させ、病気に強い作物を開発する方法。
その中から導入遺伝子が残っていないものを選び、育成しようというもの。
以上の各技術の特徴からも、「外来遺伝子が残っていない」ということにこだわっていることが、非常によく分かる。
9.SPT(Seed Production Technology)
日本で新しい種子開発の方法として日本学術会議が加えた、種子生産の技術。自家受粉作物から大量の種子を継続して増殖する方法で、雄性不稔と稔性回復遺伝子を組み合わせた「SPT遺伝子」で遺伝子組み換え系統をつくり、それを維持していく。そこから組み換え遺伝子を無くしたF1交配用のものを量産していく。
◆ノックアウト技術
「遺伝子組み換えではない」ということを強調するために、ヨーロッパで開発された技術で、その中の1つとしてゲノム編集があり、その第3世代でCRISPR-Cas9を生んだ。
例えばゲノム編集の場合はDNAを切断して遺伝子の働きを壊す技術。遺伝子の働きを止めるようなあるいは壊すような技術をノックアウト技術という。
1980年代に「ノックアウトマウス」が登場。ノックアウト技術の基本は、最初はノックアウトマウス作りだった。ノックアウトマウスというのは、遺伝子組み換えで特定の遺伝子を働かせないようにするマウスのことで、当時、病気の疾患モデル動物として、医薬品や治療法の開発につなげていこうという考え方だった。
• アンチセンス法:遺伝子組み換えで行うノックアウト技術(DNAを用いる)mRNAの働きを妨げる
• RNA干渉法:RNAを用いてmRNAの働きを妨げる
• ゲノム編集技術: DNAを切断して行う
• エピゲノム編集技術:DNAの修飾を変更して行う。今のところは、DNAのメチル化酵素をCas9(DNAを切断する酵素)の代わりに用いる。
《遺伝子操作の基本のまとめ》
◎遺伝子操作にはさまざまな方法があるが、その基本は実は変わっておらず、全ては遺伝子組換えから始まっているということが非常に重要。
◎さまざまな遺伝子操作技術があるものの、新技術含めてやっていることは全て同じである。
◎ヨーロッパで新植物育種技術というものが登場し、「外来遺伝子を入れたわけではないから規制しなくてよい」という理論で、いわゆる規制逃れを目的に開発された。
◎CRISPR-Cas9の登場で、規制逃れが一気に加速する。CRISPR-Cas9の登場で遺伝子操作は非常に簡単になったが、実は荒っぽい技術である。
◎さらにCRISPR-Cas9に代わって、DNAメチル化酵素の遺伝子をCas9の代わりに置き換えたのがエピゲノム編集技術である。