「ママ、ゲノム編集食品ってなに? 食べてみたい!」
と、もし子どもに聞かれたら、なんて答えますか?
今回の【Voice!】は、小学5年生のお子さんとお母さんにお話しを伺いました。
実は、お子さんが図書館から「ある本」を借りてきて一緒に読んだあと、お母さんはある「もやもや」を感じていると、そんな相談をいただきました。
その本は、『22世紀からきたでっかいタイ ゲノム編集とこれからの食べ物の話』という児童向けのノンフィクションで、ゲノム編集マダイを開発した京都大学の木下政人准教授の著書です。「ゲノム編集技術や、人の手によって開発されてきた食べ物の歴史を知り、未来の食や生き物のしくみを知ることができる」とされています。
お子さんに感想を聞いてみると、そんな風に話してくれました。
すると、お母さんが続けます。
ー環境中への個体の移出を防ぐために「網」で対策しているそうなんですけど、魚の卵も稚魚もすごく小さいですよね。果たして「網」で移出を完璧に防げるんでしょうか。ゲノム編集魚の卵や稚魚が環境中に絶対に交じらないなんて、言い切れないと当然考えますよね。
しかも、もし環境中に逃げてしまった場合、ゲノム編集の魚はその体の機能が壊されているせいで、うまく泳げなかったり、海水の塩分濃度の異なる場所で体の「浸透圧」というものが調節できなくなったり、自然界では生きていけない可能性があります。
そして「生物多様性に影響がない」といわれているけれど、これも実際に検証などされておらず、あくまで「環境中に移出しない」という「前提」を根拠にしているだけだと、環境省からも回答がありました。
ーそもそも「環境中に移出されない」ということも、検証したり、定期的な監査が入るわけでもありません。あくまで事前の審査で、書類で確認をしただけなんです。書類に「問題がない」というだけですよね。
ーこうした賛否のある新しい技術について、子ども向けであるからこそ、メリットだけでなくデメリットについてもきちんと伝え、考えさせる要素を与えてほしいと思いますね。
ー魚へのゲノム編集を通して、遺伝子操作の倫理的な問題を理解できますよね。ゲノム編集で遺伝子を破壊してしまうことは、その遺伝子が持っていた機能を止めてしまうことになりますが、実は遺伝子は1つの機能だけを担っているわけではありません。
例えば、この本で解説されているマダイとは別のゲノム編集魚は、食欲を抑制するレプチンというホルモンを感知する機関(レプチン受容体)をつくる遺伝子を壊すことで、満腹感が得られなくなり、どんどん食べて成長します。しかし、レプチンにはほかにも重要な機能がいくつもあって、記憶や繁殖能力、血圧などの調節の働きも持っています。そのため、ひとつの遺伝子を壊すことで、彼らが生きるうえで深刻な弊害が生じる可能性があります。ほんの少し可食部の多い魚を作り出すためだけに、人間が魚に重篤な病気を作り出してしまうということになります。
ー現状そうなりますね。ちなみに「食べたい」と思いますか?
ー私も同感です。
そして何より、「食べさせたくない」です。安全性でいえば、国も、開発した大学やリージョナルフィッシュ社さえも、「この魚を食べても安全であるかどうか」を実証する実験を行っていません。安全性は検証されていないわけです。だけど事前の書類による届出だけで「安全だ」として、流通しています。
ーわかります、難しいですよね。
ーこの問題を通して、子どもたちに1つ伝えられるとすれば、それは「いのちの尊さ」ではないかと考えていました。私たち人間が遺伝子や生命についてわかっていることはほんの一部分だけです。生命の設計図である遺伝子を「壊す」ということでその生命や環境にこの先どんな影響が起こり得るのか、またそれを食品として食べるとどのような影響が考えられるのか、誰もわかりません。研究者でさえわからないんです。
ー魚や虫、植物も自分も、どのいのちも尊く、そのいのちを全うする権利があります。だれもその尊厳を侵害することはできません。そして私たちはいのちをいただいて生きています。だからこそ、私たちが生きものとして、どのように食べ、どのように生活するかによって、それが環境にどのように影響するのか、そんなことを想像する力を育んでほしいです。
そして、母親としてこういう「もやもや」をしっかり見つめながら、子どもと話して考えていきたいですよね。
ーゲノム編集魚の養殖場も見学させてほしいですよね。情報公開もそうですが、やはり安心には透明性が不可欠です。
【4月のオンライン学習会のお知らせ】
4月のオンライン学習会は「ゲノム編集食品 基礎講座」です。
「ゲノム編集」って何? 遺伝子組み換えとどう違うの? 何が問題なの? どうしていくべき?
ゲノム編集食品にはどんな問題があるのか、基礎的なことから学べる講座です。
最近のアップデートも話しますので、情報や知識のアップデートにもオススメの講座です。
ご自身の理解を深めるためにも、誰かに伝えるときにも、確かな知識が最大の力になります。
奮ってご参加くださいね!お楽しみに!
《オンライン学習会:ゲノム編集食品基礎講座》
日時:2025年4月21日 20:00〜21:30
講師:印鑰(いんやく) 智哉(OKシードプロジェクト事務局長)
◆お申込みはコチラ
https://save.okseed.jp/eventapplybcs
《ご支援をお願いします》
OKシードプロジェクトのすべての活動は広く市民の方の寄付だけが頼りです。少額の寄付を広い市民の方たちからいただくことで、政府や大きな組織に忖度することなく、市民の立場で活動することができます。もっともOKシードプロジェクトの活動の多くが無償ボランティアに頼っており、活動を拡げるうえでも、さらなるご支援が必要になっています。
OKシードプロジェクトでは、活動する方にお金がなくても情報が得られるように、すべての情報は無料で提供しております。一方で、OKシードプロジェクト自体が活動を維持し、拡げるためにはお金は不可欠です。もし、少額の寄付なら可能だという方は、ぜひご支援ください。クレジットカードあるいは銀行振込でご支援いただけます。
\マンスリーサポーターも募集中!/
◆ご寄付はコチラから
https://v3.okseed.jp/donateus



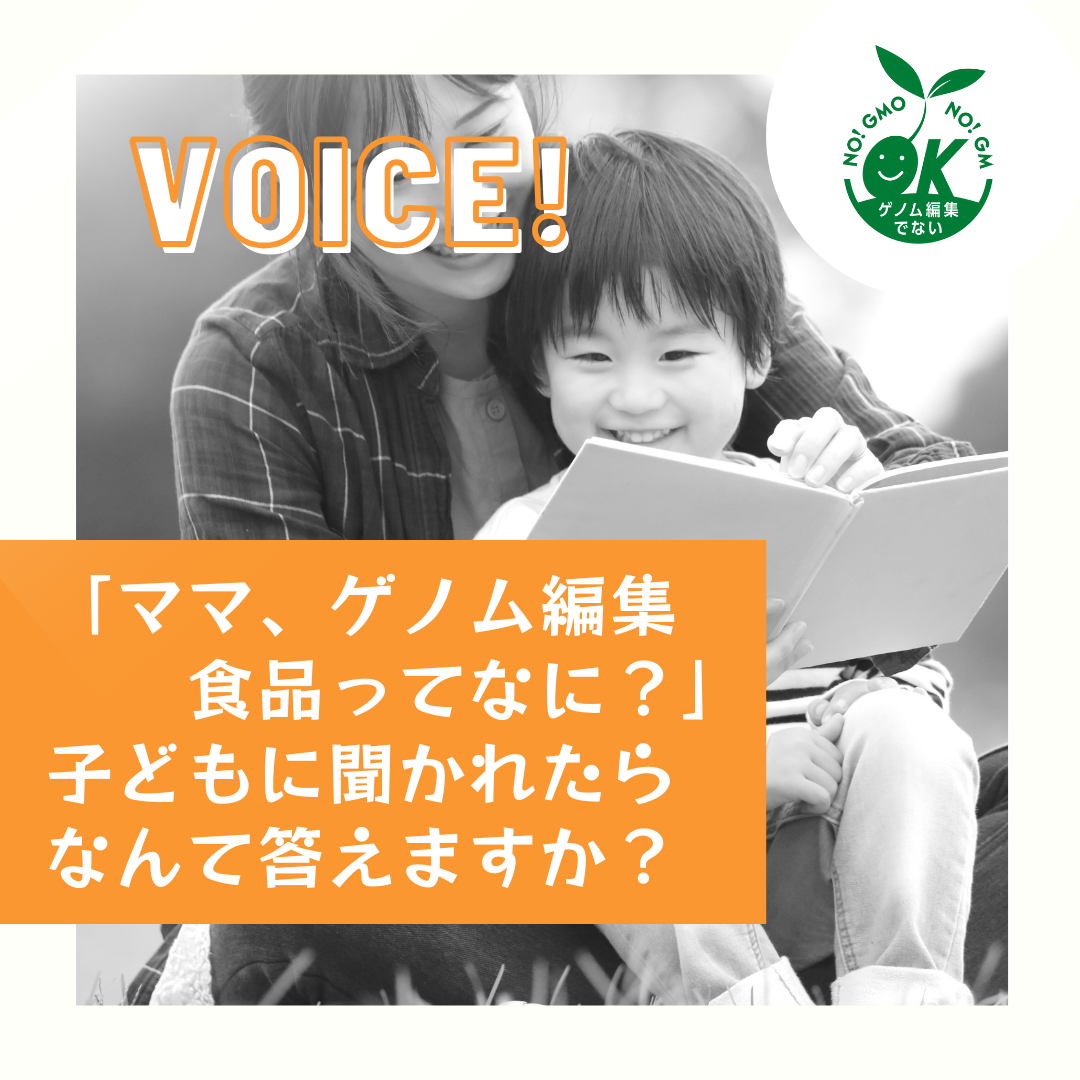

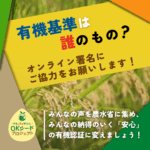


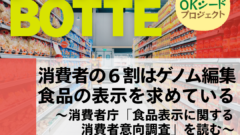
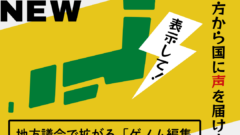

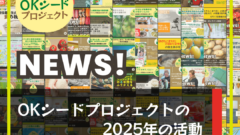
はじめて聞く難しい言葉がいっぱいだったけど、わかりやすかったから全部読めた。
ゲノム編集の仕組みがわかったよ!」